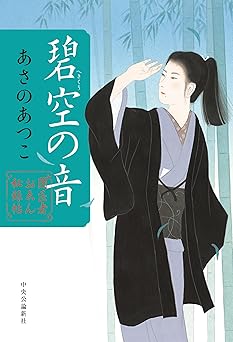「あっしも、花魁の芯の強さは感じてやす。けど、だからといって、一人で生きていけると先生が言い切っちまうのは、ちょいと酷じゃねえですか。花魁は、本気で先生に惚れてるじゃねえですか。先生がいるから、生きていける。そう想って、恋焦がれてるとあっしは……いや、あっしだけでなく、惣名主も見抜いてやすぜ」
吉原惣名主、川口屋平左衛門(かわぐちやへいざえもん)。白髪の目立つ髷を結いながら、生き生きとした眸を持つ老人だった。その眸が、ときに冷たく、ときに鋭く人の心内を抉る場面に何度か出くわした。大店(おおだな)の主然とした品のよい風貌の下に、爪も牙も隠している。吉原惣名主の前で、おゑんは一瞬の油断もできなかった。それこそ首を刎ねられかねない心地すらする。
「まあ、あっしが見抜けるぐれえのことは、惣名主ならとっくにわかってたでしょうがね」
「つもり、だけかもしれませんね」
湯呑の中身を飲み干す。
「え、つもりだけ?」
「ええ、甲三郎さんも川口屋さんも、見抜いたつもりになっているだけかもしれませんよ」
「あっしたちが見誤っていると?」
「ふふ、まさかって顔ですね」
甲三郎が、自分の顔をつるりと撫でた。眉間に皺ができている。
「まさかでやす。花魁は先生に惚れてやすよ。心底からね。そこんとこは揺るがねえ。あっしはともかく、惣名主の目は誤魔化せねえでしょう」
「誤魔化すつもりなんてありませんよ。けど、呆れはしますね」
甲三郎の皺がさらに深くなる。
「何に呆れるんです、先生」
「おまえさんたちの自惚(うぬぼ)れ具合にですよ」
おゑんは指を一本立てると、その先を甲三郎に向けた。真っ直ぐに伸ばす。指先を避けることなど雑作もないだろうに、甲三郎は僅かも動かなかった。そのまま伸ばし、動かない男の眉間に当てる。
「女の心は底無しですよ。吉原惣名主だろうが首代の元締めだろうが、男風情が覗き込んで何が見えるわけもなし。それを見抜いただの、わかっていただの、訳知り顔に口にする。自惚れも大概にするんだね。おこがましいにも程があるってものさ」
指先に少し力を込める。皺はもう消えていた。
「……と、川口屋さんにお伝えくださいな」
さて、あの海千山千の商人は、あたしの言い分をどう受け止めるかねえ。
他愛もない戯言と笑い飛ばすか、小生意気な物言いだと腹を立てるか。どちらでもあるまい。「それでは、先生の覗き込んだ人の心には、何がどのように見えましたかな」と、真顔で問うてくるのではないか。
「伝えておきやす」
背筋を真っ直ぐに立てたまま、甲三郎が答えた。おゑんは指を握り込む。
「それでも、花魁が先生に逢いたがっているのは事実でやしょう。心の内に何があろうと、事実でやす。だから、お返事をいただいて帰りやすよ」
物言いも真っ直ぐだ。こういうところが、甲三郎らしい。黙り込み、相手を圧してくるか、真っ直ぐに語り、相手の懐に飛び込んでくるか、だ。
平左衛門ほど老獪ではないが、一息に急所を突いてくる怖さがあった。
おゑんは頷き、話の向きを僅かにずらしてみる。
「もう一度、お尋ねしますけど、お小夜さんは身体を悪くしているわけじゃないですね」
「へえ、臥せっているとかはありやせんぜ」
「そうですか。じゃあ、先刻と同じことを尋ねなきゃなりませんね。甲三郎さんの目から見ても大丈夫そうに見えましたか。そして、何かありませんでしたか。お小夜さんの周りで、何か変わったことが。どんな些細なことでも構わないんです。むしろ、誰もすぐには気付かないような、けれどいつもとは違う出来事……ありませんでしたか」
「変わったこと……」
甲三郎が腕を組み、天井を仰ぐ。何もない宙を見詰める。
大門(おおもん)の外、ごく当たり前の世間、朝と共に目覚め、動き、働き、日が沈めば眠る。そんな世間とは全く別の則(のり)で、吉原は蠢いている。
世間の変事が吉原の尋常であることは、少なくない。甲三郎は、そこを思案に入れながら宙を見ているのだ。
「とりわけ、何もなかったかと思いやす。ああ、羅生門河岸(らしょうもんがし)の女郎が一人、亡くなりやした。急に具合が悪くなって、三日ほど寝込んで逝っちまったとかで」
「そうですか。まぁ三日患っただけなら、御の字かもしれませんねえ」
「全くで」
羅生門河岸と呼ばれる東河岸、浄念河岸(じょうねんがし)と呼ばれる西河岸、そこに軒を連ねる河岸見世(かしみせ)で働くのは、廓内で最も下層の遊女たちだ。病になろうと傷を負おうと医者が呼ばれることは、まずない。そのまま捨て置かれる。
長引かず三日で逝けたのなら幸運だったと河岸見世の女たちも、頷き合っただろう。
「後は……ちょっとした刃傷沙汰が二つ三つあって、男が一人大怪我をしたとか亡くなったとか耳に挟みやしたが、それぐれえで、格別何も起こっていやせんねえ」
甲三郎は、“ちょっとした刃傷沙汰”を変事の内に入れなかった。単なる騒ぎの範疇でしかないのかもしれない。人が死のうが殺されようが、だ。
「そうですか。お小夜さん自身にも周りにも何事もない。だとしたら……」
だとしたら、この恋文の意図はどこにある?
「先生、おかしかねえですか」
甲三郎が身を乗り出した。
「花魁は先生に逢いたくて、想いが募って、こうやって文を綴ったんじゃねえんですか。なのに何で、考え込むんでやす。それとも、その文には気になることが書いてあったんで」
「いえ、中身はこれといって気にはなりませんね。美しい手跡の見事な文ですよ。ただ、あたしが引っ掛かっているのは、中身より文そのものです。お小夜さんが、なぜこれを寄越したか。それが、妙に気になりますね」
「ですから、先生に逢いたくて、思い余った末の……」
甲三郎が口ごもる。おゑんがかぶりを振ったからだ。
「芝居ならそういう筋書きもあるでしょうよ。もっとも吉原一の花魁の相手役となると、姫路藩あたりの殿さまでなければ務まらないでしょうが。けどね、甲三郎さん、あたしは芝居ではなく現の話をしているんですよ。現のね」
おゑんの物言いに何を感じたか、甲三郎は前のめりになっていた身体を起こし、居住まいを正した。口を結び、手を膝に置く。本気で耳を傾けようとしているのだ。
(この章、続く)