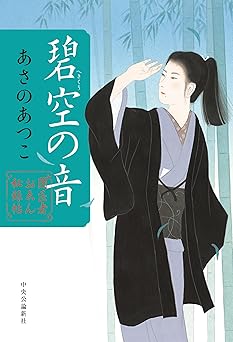「これはまた、えらくおもしれえところでやすね」
甲三郎が屈託のない笑みを浮かべた。
「おや、初めてでしたかね。調合部屋ですよ。まぁ、末音の本丸といったところですかね」
「じゃあ、ご領主さまに逆らえば首が落ちやすね」
「首を刎ねられたりはしませんよ。毒を盛られる心配は、たんとありますけどね」
「そりゃあ、おっかねえや。肝が縮みやす」
「まあまあ、いい大人が二人、ようそこまで戯言(ざれごと)を言えますのう」
末音が呆れた風に、苦笑いを浮かべた。
戸口近くに座った甲三郎の前に、湯呑を置く。湯気が上がっていた。
「どうぞ、召し上がれ」
「あ、へえ。あの、末音さん、これは……」
「薬茶でございますよ。身体の芯を温めて、気を楽にいたします。あなたは、どうも、いつもいけませんからの」
「いけない? 何がでやす」
「いつも気を張っているのが、いけませんの。人は張り詰めたままでは生きられませぬから。どこかで緩む塩梅を覚えねば、そのうち……」
「末音さん、途中で口ごもらないでくだせえ。何か、ぞくっとするじゃねえですか。塩梅を覚えなかったら、どうなるんで」
「そりゃあ、おゑんさまに詳しくお聞きなされ。さてさて、雨が降り出す前に、薬草を取り込みますかの」
末音はしっかりした足取りで、部屋を出て行った。甲三郎が肩を竦める。
「おやまあ、末音が他人をからかうなんて、ずい分と珍しいねえ。甲三郎さん、相当気に入られてるんじゃないかい」
「え? さっきのは、おれをからかったんでやすか」
「半分はね。けど、半分は本当のことですよ。ずっと張り詰めていたら、人は必ず折れちまいますからね。けどまあ、甲三郎さんは大丈夫でしょう。ご自分の緩め方も研ぎ澄まし方もご存じでしょうからね。あたしは心配していませんけれど」
「いや、先生が心配してくれるなら、それはそれで嬉しいような心持ちになりまさぁ。あ……美味い」
薬茶をすすり、甲三郎が口を窄(すぼ)めた。
「ほんのり甘くて、でも茶の風味もしっかりしていて……うん、美味い。確かに、身体が温(ぬく)もりやす。これ、どこの茶葉でやすか」
「さあてね。甘いのは蜂蜜が入っているからだと思いますが、他は何をどう調合したのか、あたしにもさっぱりなんですよ。末音は薬草の扱い方に誰より長けておりますからね」
おゑんも、末音が淹れかえてくれた茶を口に運ぶ。さっきのものより花の香りは薄いが、甘みは濃い。確かに、芯から温かくなる気がした。
「この薬茶、お小夜さんへ託(ことづ)けましょうかね。気持ちが落ち着くかもしれません」
甲三郎が湯呑から顔を上げる。
「ずい分と冷てえ言い方でやすね、先生」
「冷たい? あたしがですか」
「違いやすか。いや、あっしは文の中身は知りやせん。けど、あっしを座敷に呼んで、それを渡してきたときの花魁の眼は見やした。顔も見やした。声も聞きやした。それこそ、とてつもなく張り詰めて、真剣でやしたぜ、先生」
おえんは僅かに眉を顰めた。
「甲三郎さん、まさかとは思いますけど、おまえさん一人の裁量で文を届けに来たんじゃないでしょうね」
花魁の文を勝手に吉原の外に持ち出す。
許されることでは、ない。
「惣名主から言われておりやす。花魁から先生への文なら、中身を確かめずそのまま届けて構わないと。むろん、美濃屋のご主人も納得してやす」
久五郎が惣名主の意向に異を唱えることは、まず、あるまい。それほど度胸があるわけがないし、それほど思案が回らない間抜けではない。
「なるほどね。あたしなら害はないということですか。ふふ、まあ花魁の間夫(まぶ)になる心配はありませんからねえ。吉原としては大目に見てもよいと、判を押してくれたわけですね」
遊女の色恋が良しとされるのは、飽くまで商いの上でのこと。むしろ、客を惹き付ける手練手管として勧められる。けれど、そこに本気が混ざるなら、決して犯してはならぬ吉原の掟に背いたものと見なされる。
お小夜、いや、安芸ほどの身となれば、罰せられる、つまり始末されるのは安芸本人ではなく相手だ。邪魔者として取り除かれる。大方は誰にも知られぬまま葬られてしまうのだ。
「害はないというより、先生がいなくちゃ困るってのが、惣名主の本音じゃねえですかい」
さらりと、甲三郎が告げた。
「先生に何かあったら、花魁は死にやすよ」
やはり、淡々とした口調で続ける。
「もしかしたら、惣名主の目の前で自分の喉を掻き切るぐれえはするかもしれません」
おゑんはゆっくりと茶をすする。
「甲三郎さん、世話物の芝居でも観たんですか」
「へ? いや、このところ、とんと観てやせんが」
「ふふ、それにしては、えらく芝居がかった話をするじゃないですか」
甲三郎の唇が僅かに尖る。不満げな表情だ。能面のように一切の情を消してしまえるくせに、子どものようにころころと表情を変えもする。何とも不思議な男だ。
けれど、正体が掴めなくて、したたかでしぶといというのなら、男より女の方が勝っているかもしれない。
「お小夜さんは死んだりはしませんよ。少なくとも、自分で自分にけりをつけるような真似は決して、しませんね」
「言い切れるんで」
「ええ。この世は、わからないことだらけだけれど、そこのところだけは確かです。お小夜さんは強いですからね。折れも倒れもしませんよ。そして、生きるために誰も要らない。己だけを頼りとして前に進める。そういう人なんです」
甲三郎の唇はまだ、心持ち尖っている。納得できていないのだ。
(この章、続く)