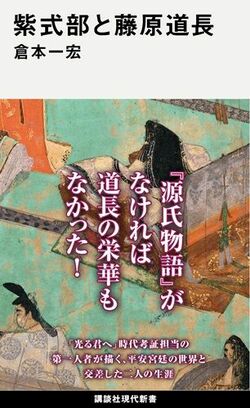都を恋う
京を出て鴨川を渡り、粟田口から山科を経て逢坂(おうさか)山を越え、一行は大津の打出浜(うちいでのはま。現大津市松本町)から舟で琵琶湖西岸を北上した。
打出浜というのは逢坂越えの谷口より打出た浜の意味で、『万葉集』をはじめ、『大和物語』『蜻蛉日記』『枕草子』『源氏物語』『更級日記』など多くの文学作品に登場する名所である。
現在の浜大津から瀬田川河口にかけての湖岸、におの浜のあたりであろう。
今も風光明媚な浜で、「式部の庭」「さざなみの庭」「源氏の庭」と名付けられた花壇が設置されている。
紫式部は、高島の三尾が崎(現滋賀県高島市安曇川町)の湖岸(勝野のことであろう)で、漁師が網を引く姿を見て、早くも都を恋う歌を詠んでいる。
三尾の海に 網引く民の てまもなく 立ち居につけて 都恋しも
(三尾が崎で網を引く漁民が、手を休めるひまもなく、立ったりしゃがんだりして働いているのを見るにつけて、都が恋しい)
また、夕立が来そうで空が曇り、稲妻が閃いて波が荒れた時には、これまで舟に乗る経験もなかった紫式部の心は落ち着かなかった。
かきくもり 夕立つ波の あらければ 浮きたる舟ぞ しづ心なき
(空一面が暗くなり、夕立を呼ぶ波が荒いので、その波に浮いている舟は不安なことだ)
「浮き舟」という語に、やがて自分の作る物語世界で大きな意味を持たせることになろうとは、この時はまだ、まったく気づいてはいなかったことであろう。