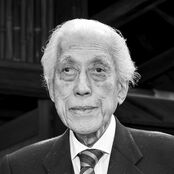クラスには、当時の朝鮮、満洲(現・中国東北部)、台湾出身の学生やアメリカ人2世などさまざまな同級生がいました。あのとき、もし同志社に行っていなければ、私の生きる世界はずっと小さいままだったでしょう。父の勧めは正しかったのです。
ところが1943年、私が大学2年生になったとき、事態が急変しました。戦況の悪化にともない、突如として大学の文系学生の徴兵猶予が取り消されたのです。徴兵猶予とは、大学を卒業するまで徴兵を延期してもらえる制度のこと。「うわー、参ったなあ」と正直、思いました。
しかし、軍役は義務であり責任です。逃れるわけにはいきません。その年の9月に徴兵検査。人より体が大きく、馬術や剣道で鍛えてきた私は、当然ながら一発合格です。
検査の後、「君は、陸軍と海軍、どちらに行きたい?」と聞かれ、「海軍へ行きます!」と答えました。面接官は、「陸軍もいいぞ」と言いながら書類に目を通し、「あ、君は水上機の訓練をしていたのか」と。
その頃、私は琵琶湖畔の水上機乗員訓練所に通い、単独飛行ができるようになっていたのです。おそらくそれが決め手になったのでしょう。京都府の海軍舞鶴海兵団への入団が決まりました。