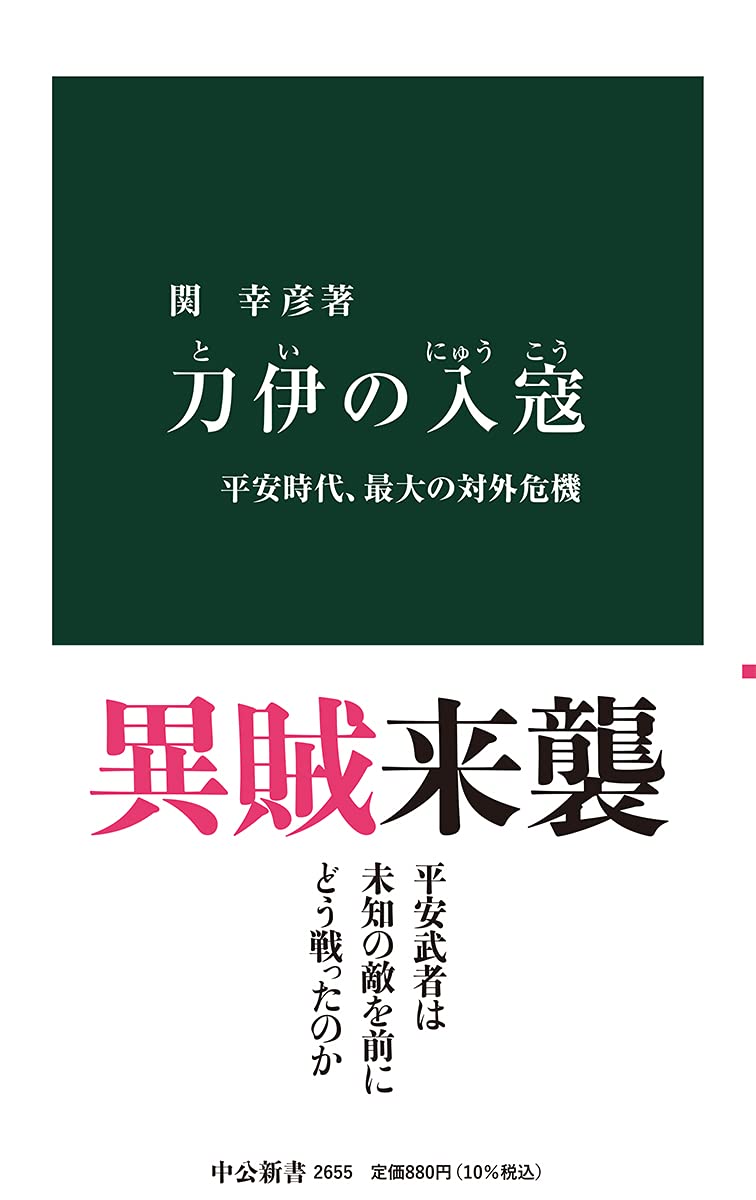国力の劣等意識
10世紀以降の新羅来寇事件も重なり、わが国は対外的には消極外交にあった。
当初この刀伊襲来は新羅海賊(あるいは後継の高麗の勢力)の再来と解されていた。それほどまでに対新羅(高麗)への脅威が大きかった。
さらに王朝貴族には、大陸情勢の中で国力の劣等意識もあった。かつての新羅への負の記憶は刀伊戦での捕虜に高麗人がいたことで、来襲の主体に明瞭さを欠き、高麗の犯行と解する向きもあった。
隆家が対馬方面に向かった武者たちに、「新羅ノ境ニ入ルベカラズ」と訓令を与えたのも、右に述べた事情が伏在していたはずだ。
ちなみに、この時期を含め、わが国の版図の認識は漠然とながら存在した。北は陸奥国の外ヶ浜から南は九州の南西海上の鬼界ヶ島だ。
いうまでもなく琉球そして蝦夷地が領域化されるのは近代以降である。王朝時代を含めての北と南の範囲として、『曽我物語』の源頼朝・安達盛長の夢のエピソードを持ち出す必要もあるまい。
源頼朝が見た夢は、左の足を広げて外ヶ浜と鬼界ヶ島を踏みつけ、両袖に日月を入れ、南に向かって歩むという、天下統合を暗示するものであった。
その点では、王朝貴族が共有する版図として、実録(日記)に西の境を対島・壱岐としているのは興味深い。
*本稿は、『刀伊の入寇-平安時代、最大の対外危機』の一部を再編集したものです。
『刀伊の入寇-平安時代、最大の対外危機』(著:関幸彦/中公新書)
藤原道長が栄華の絶頂にあった1019年、対馬・壱岐と北九州沿岸が突如、外敵に襲われた。東アジアの秩序が揺らぐ状況下、中国東北部の女真族(刀伊)が海賊化し、朝鮮半島を経て日本に侵攻したのだ。道長の甥で大宰府在任の藤原隆家は、有力武者を統率して奮闘。刀伊を撃退するも死傷者・拉致被害者は多数に上った。当時の軍制をふまえて、平安時代最大の対外危機を検証し、武士台頭以前の戦闘の実態を明らかにする。