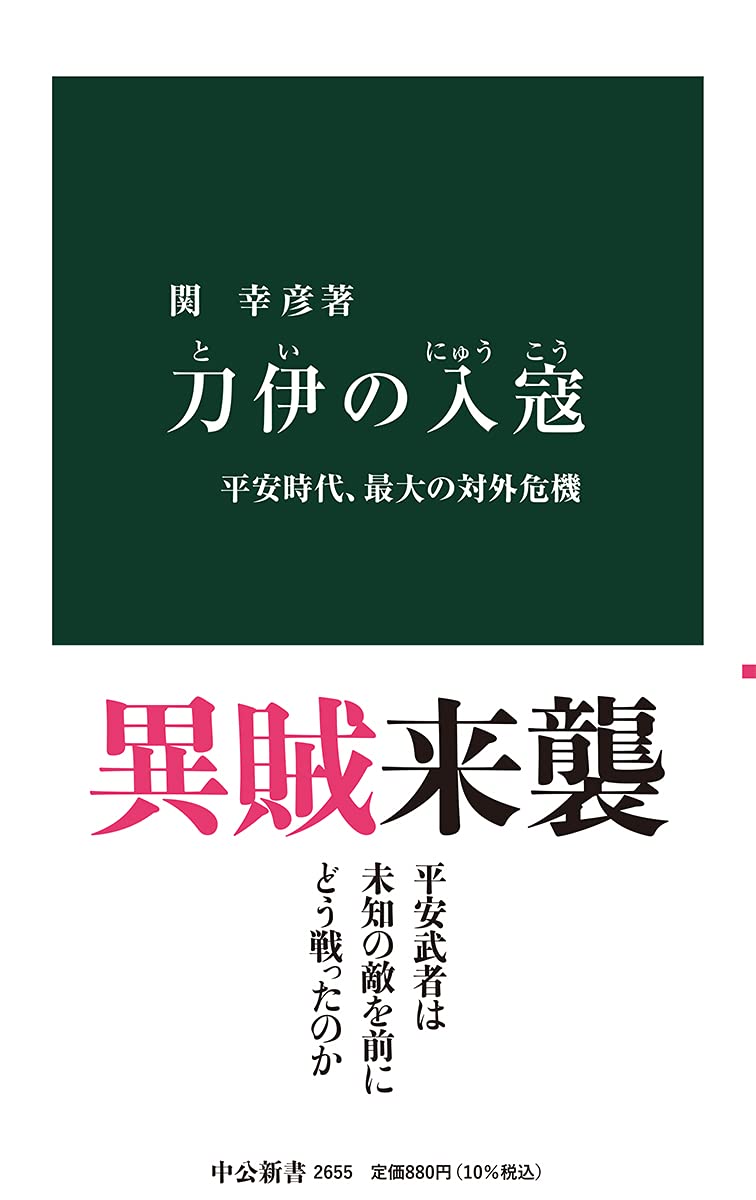寛仁年間-刀伊の襲来
最後は寛仁年間(1017~21)。
後一条天皇が即位し、道長の嫡子頼通が摂政・関白に。道長の血脈による摂関の独占が決定的となった。
三条院が死去し、その皇子敦明が東宮を辞退する。これに代わって彰子所生の敦良親王(のち後朱雀天皇)の立太子が実現する。
寛仁2年(1018)3月には道長の娘威子が後一条天皇に入内した。『小右記』所載の有名な歌「この世をばわが世とぞ思ふ望月の欠けたることもなしと思へば」はこの時期のものだ。
寛仁3年3月に道長は出家、頼通が関白となる。そして刀伊(女真)が対馬を襲ったのは、この時期のことだった。
*本稿は、『刀伊の入寇-平安時代、最大の対外危機』の一部を再編集したものです。
『刀伊の入寇-平安時代、最大の対外危機』(著:関幸彦/中公新書)
藤原道長が栄華の絶頂にあった1019年、対馬・壱岐と北九州沿岸が突如、外敵に襲われた。東アジアの秩序が揺らぐ状況下、中国東北部の女真族(刀伊)が海賊化し、朝鮮半島を経て日本に侵攻したのだ。道長の甥で大宰府在任の藤原隆家は、有力武者を統率して奮闘。刀伊を撃退するも死傷者・拉致被害者は多数に上った。当時の軍制をふまえて、平安時代最大の対外危機を検証し、武士台頭以前の戦闘の実態を明らかにする。