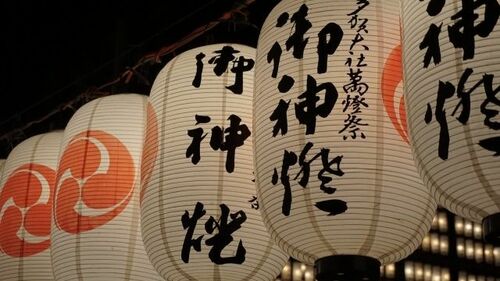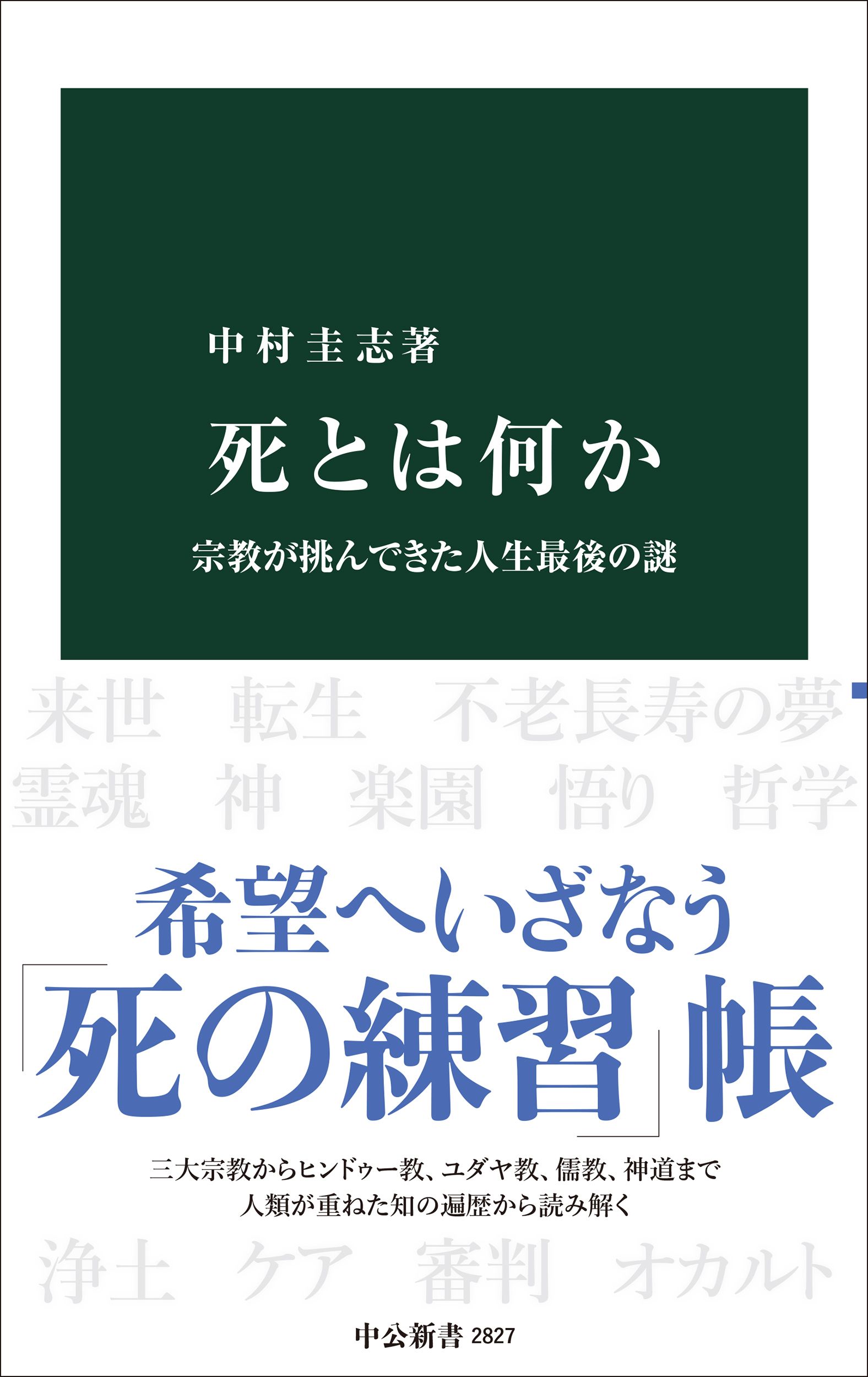身体と精神の二つを対等の実在と考える霊肉二元論
この《物理主義》と対立する立場は、《二元論》と呼ばれる。身体と精神(心、魂)の二つを対等の実在と考える霊肉二元論である。
こちらの立場をとるならば、人間は死んでも<つまり物理的身体が朽ち果てても>精神ないし心の部分が一種独特な実在として生き続ける可能性がある。
身体から着脱可能な精神・心の座は「霊魂」と呼ばれる。表現は「霊」でも「魂」でもいい。《二元論》は、伝統的な宗教の立場だ。
仏教、ヒンドゥー教、キリスト教、イスラム教といった古典的なビッグネームの宗教に限らず、多くの宗教伝統、民間信仰、新宗教では、人間 を超えた存在として「神仏」のようなものを想定すると同時に、人間の本質部分として「霊魂」のようなものを想定している。
こうした宗教的人間観によれば、人間を構成する霊魂と身体がくっついた状態がいわゆる「生」であり、この二つが離れた上に身体のほうが消えてしまった状態が「死」なのである。
「死」と呼ばれつつも霊魂は消失していないので、死は一種の「生」である。冥界や天国などにおける生、もしくは再びこの世に転生する生である。
※本稿は『死とは何か-宗教が挑んできた人生最後の謎』(中央公論新社)の一部を再編集したものです。
『死とは何か-宗教が挑んできた人生最後の謎』(著:中村圭志/中央公論新社)
死んだらどうなるのか。天国はあるのか。できればもう少し生きたい――。
尽きせぬ謎だから、古来、人間は死や来世、不老長寿を語りついできた。その語り部が、宗教である。本書では、死をめぐる諸宗教の神話・教え・思想を歴史的に通覧し、「死とは何か」に答える。日本やギリシアの神話、ユダヤ教、キリスト教、イスラム教から、仏教、ヒンドゥー教、そして儒教、神道まで。浮世の煩悩を祓い、希望へ誘う「死の練習」帳。