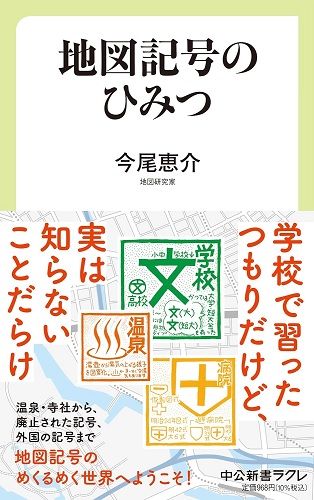電灯が普及したあとの地図
その後、戦前の代表的図式である「大正6年図式」では「電線(高圧)」「電線(普通)」と2分類したのだが、同じ図式が引き続き適用されているはずの昭和10年(1935)に刊行された部内資料『地形図図式詳解』(陸地測量部)には「電線(高圧)」と「電線(通信線)」のように分類が改訂されている。
一般家庭に電灯がかなり普及したこの段階では、街中に張り巡らされたものを律儀に描く意味がなくなったからだろう。
これを反映したかのような記述が同書にある。「山間僻地等ニ稀ニ存スル電灯線ノ稍(やや)長ク連絡セルモノノ如キハ之ヲ描クコトアリ」というくだりだが、この頃にはすでに市街地や人里に高密度で張られた普通電線は対象外となっていたはずだ。
戦後の舗装道路の記号がほどなく廃止されたのと同様、対象があまりに増えると煩雑になり過ぎるし、そもそも記号化する意味がなくなる。
なお関西地区で明治17年から整備された「仮製2万分1地形図」の図式は「電線」の表記であるが、時代から判断して電信線らしい。
電信開通時、「ハリガネがいち早く手紙を届けてくれると聞いて、電線に手紙をくくり付けた」という都市伝説もあるが、それから150年でずいぶんと世の中は変わったものである。
※本稿は、『地図記号のひみつ』(中央公論新社)の一部を再編集したものです。
『地図記号のひみつ』(著:今尾恵介/中央公論新社)
学校で習って、誰もが親しんでいる地図記号。地図記号からは、明治から令和に至る日本社会の変貌が読み取れるのだ。中学生の頃から地形図に親しんできた地図研究家が、地図記号の奥深い世界を紹介する。