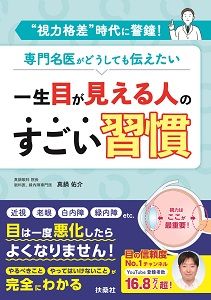必ずしも“悪”とは言えない
乱視は必ず0にしないといけないものでもないですし、ある程度の乱視は焦点深度(鮮明に見える範囲)を深める働きもあり、乱視のおかげでピントを合わせられる範囲が広くなることもあります。
ですので、乱視が必ずしも“悪”にはならないとも言えます。
矯正が必要であるかどうかは、乱視であるかどうかではなく「どの程度の乱視なのか」が重要になります。
ある程度以上の場合には視力の低下だけではなく、眼精疲労の原因になってしまいます。ですので、自分にどの程度の乱視があるかを理解したうえで眼鏡、コンタクトレンズでの矯正を行うようにしましょう。
※本稿は、『一生目が見える人のすごい習慣』(扶桑社)の一部を再編集したものです。
『一生目が見える人のすごい習慣』(著:真鍋佑介/扶桑社)
視覚は生きていく中で最も重要な感覚です。私たちは日常生活で得られる情報の8割を視覚から得ていると言われています。ですので、目という器官の健康を維持し、一生目が見えるようにしていく習慣作りが大事です。いくつかの急性疾患を除き、視力や視野は急激に悪くなるものではなく、だんだんと、ゆっくりと、しかし着実に悪くなっていきます。人生100年時代と言われる今、ずっと目が見える生活を送っていくなら、早めの検査、早めの生活改善、早めの治療が本当に大事になっていきます。日々の生活の中での食事や運動、睡眠と些細なことでも毎日続けていけば確実に変化があります。