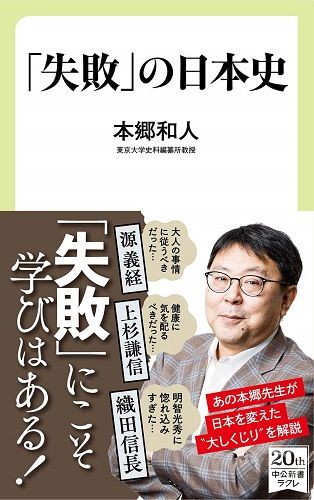現代まで引き継がれている「切り放ち」
胸が悪くなるような話ばかりしましたので、最後に少し明るくなる(?)話をご紹介しましょう。
江戸市中で10万人超の犠牲者を出したといわれる明暦の大火(明暦3年・1657年〉に際し、石出帯刀(諱は吉深)は収監者を火から救うため、独断で「切り放ち」(期間限定の囚人の解放)を行いました。
彼は収監者に対し「火から逃げられたら、必ずここに戻ってくるように。そうすれば死罪の者も含め、私の命に替えて必ずその行動に報いよう。だが、もしこの機に乗じて逃げるなら、地の果てまで追い、その者のみならず一族郎党全てを成敗する」と伝え、猛火が迫る中で数百人余りの「切り放ち」を実施しました。
収監者たちは涙を流して帯刀に感謝し、約束通り全員が牢に戻ってきたといいます。
帯刀は「罪人といえど約束を守ったのは天晴れである。このような振る舞いはほめられるべきである」と評価し、老中に死罪も含めた罪一等の減刑を嘆願。幕府も収監者全員の減刑を実行する事となったそうです。
この処置はこれ以後江戸期を通じて「切り放ち後に戻ってきた者には罪一等減刑、戻らぬ者は死罪(後に「減刑無し」に緩和された)」とする制度として慣例化されました。また明治になると明文化され、現代まで引き継がれているそうです。
実際に関東大震災や太平洋戦争の空襲の時に、受刑者を「切り放ち」した記録が残っています。
大河ドラマ「べらぼう ~蔦重栄華乃夢噺(つたじゅうえいがのゆめばなし)〜」
【放送予定】2025年1月~
【作】森下佳子
【主演】横浜流星(蔦屋重三郎 役)
【制作統括】藤並英樹 【プロデューサー】石村将太、松田恭典 【演出】大原 拓、深川貴志
【放送予定】[総合]日曜 午後8時00分 / 再放送 翌週土曜 午後1時05分[BS・BSP4K]日曜 午後6時00分 [BSP4K]日曜 午後0時15分