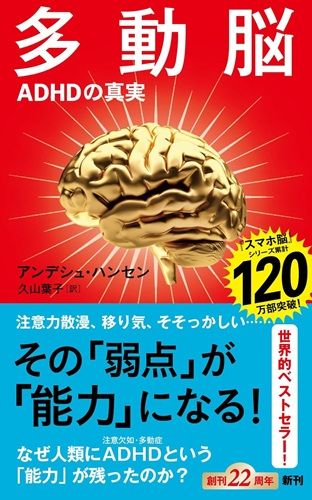現代社会で重荷になる
このように、すぐに気を取られる人の方がサバンナで生き残れる確率が高かったはずだ。さらに想像を膨らませ、2人を現代に連れてきて教室なりオフィスなりに座らせてみるとしよう。すると今度はすぐに気を取られる人の方が優秀だという保証はない。
教室やオフィスではかさっという音にも反応する敏感さが足を引っ張ることになる。クラスメートが咳をしたり椅子をずらしたり、車が外を通っただけで先生の話を聞けなくなってしまうのだから。
すぐに気を取られない人の方は重要ではない情報を排除するのが得意で、ウサギやライオンには気付けなかったかもしれないが、先生の話には集中できる。こうして2人の立場は入れ替わった。サバンナでは〈強み〉だった特性が教室やオフィスでは〈問題〉になるのだ。
何もかもに気を散らされて集中できない──私が診てきたADHDの患者たちもそう言っていた。些細なことで集中が途切れ、どうしてもそっちを見たいという誘惑に勝てない。換気扇が回る音、外を通り過ぎる車、チクタクいう壁時計、4列前で咳をするクラスメート。
常にそばにあるスマホは言うまでもない。刺激が常に最大音量になっている状態だ。その上、頭の中では何百もの考えがぐるぐる回っている。そういったことに集中を邪魔されているのだ。
祖先の例でもわかるように、刺激に対して敏感なことが〈弱み〉だとも言い切れない。時と場合によっては〈強み〉にもなるのだ。誰も気付けなかったウサギに気付き、それを食べて生き延び、遺伝子を子孫に伝えたのはすぐに気を取られた人なのだから。
しかし人間は急激にライフスタイルを変化させてしまった。サバンナを出て食べ物を狩るのをやめ、クリック1つで食べ物が家に届く世界を創り上げた。サバンナからフェイスブックまでかかった時間はわずか1万年──1万年というと永遠のように感じられるかもしれないが、進化の見地からすると瞬く間だ。
その間、人間の脳は基本的に変わっていない。サバンナで生活するために進化した脳を今でも持っているが、当時命をつないでくれた特徴が現代社会では重荷になっている場合があるのだ。
今ではADHDと呼ばれるようになった特徴──それは過去のライフスタイルに適応するよう進化したからこその特徴なのだろうか。かつては役に立ったが生活が激変したため負担になってしまったのか? 私はそうだと思う。
※本稿は、『多動脳:ADHDの真実』(新潮社)の一部を再編集したものです。
『多動脳:ADHDの真実』(著:アンデシュ・ハンセン 翻訳:久山葉子/新潮社)
シリーズ120万部突破!『スマホ脳』著者が問う
「なぜ人類は進化の過程でADHDという〈能力〉が必要だったのか?」
生きづらさが強みに変わる世界的ベストセラー!