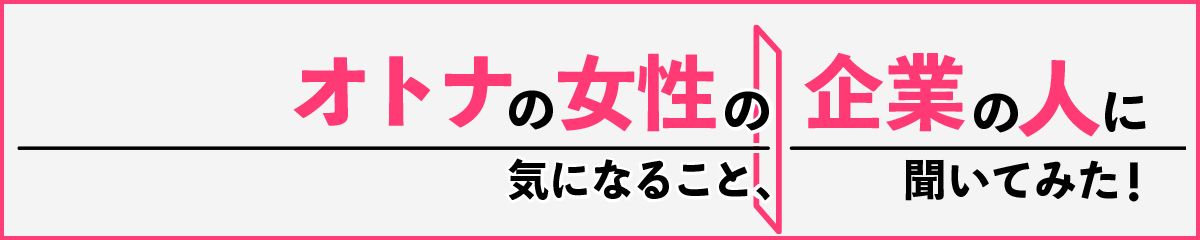この記事の目次
キッコーマン座談会 参加の方々
1:母の愛情が詰まった食卓の記憶
2:戦争が刻んだ食への執着
3:食事は人間関係のバロメーター
4:キッコーマンと「おいしい記憶」の出会い
5:食育への思い
6:現代の食卓事情「一緒に食べてるのに孤食ですよ」
7:記憶に残る味と体験
8:地域による味の違い
9:対談を通じてわかる「おいしい記憶」のこと
ネットで話題の「夫(元木さん)の体重減少」について
4:キッコーマンと「おいしい記憶」の出会い
ー大津山さんは2004年に会社で食育プロジェクトを立ち上げた際、小田桐さんに監修を依頼したのですね。
大津山:2005年の食育基本法制定直前に、キッコーマンが食育宣言を出す際、小田桐さんから「おいしい記憶をつくりたい。」という企業メッセージの提案を受けました。それがそのまま、弊社のコーポレートスローガンになっています。それが、ウェブサイト「おいしい記憶」の根幹になり、多彩な「おいしい記憶」のコンテンツを展開しています。小田桐先生が手掛けてくださった企業CMの動画もあり、コンテンツの視聴数は、このところ顕著に伸びています。
ーお2人を結んだのは、意外な縁だったようですね?
大津山:私が5歳から10歳まで利尻島に住んでいた時期に、偶然にも小田桐さんのお父様が利尻町長を務めていらっしゃったのです。
5:食育への思い
ー食育プロジェクトや当時社会問題化していた「孤食」についてどう思われますか?
小田桐:ご家庭では、お父さんも子どももお母さんも、それぞれ働く時間や学校に行く時間が別々で、みんなそれぞれ勝手に食べて勝手に出て行くみたいな、そういう傾向がだんだん強まってきているのを感じていました。食へのなんていうかな、温かさとか、食が持っている幸せな感じがありますよね。そういったものがやっぱり薄れつつあったんです。
ーその解決策として提案したのが「つくる、たべる、はなす。」というキャッチフレーズだったのですね?
小田桐:つまり「おいしい記憶」というのは、「幸福の記憶」だと言ってもいいと思うんです。幸福な記憶をたくさん持っている人っていうのが、やっぱり幸せな人だと思うのです。