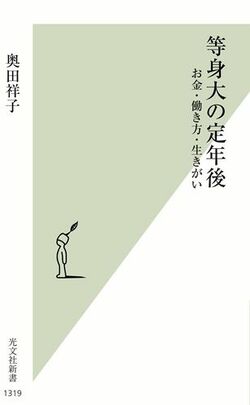「CSR担当のチャンスを生かしたい」
林田さんとは、大手企業を中心にCSRに関する動きが活発化しだし、「日本のCSR経営元年」とも呼ばれる2003年に出会った。当時37歳で、中小メーカーの経営企画部で課長補佐を務め、CSRを担当して数か月という時期だった。
大手企業が経営トップ直結の専門組織などを設置して担当役員を任命し、CSR経営に乗り出し始めたのに対し、林田さんが勤務する会社では専門部署を設けることなく、経営企画部内に「CSR担当」として、彼と入社年次が5年下の30代前半の部下の2人だけ。役員会に諮るためのCSRの活動内容の選定にあたっていた。
「これからの時代、CSR経営は企業の存続と発展のために欠かせない。そう自信を持って言えます。日本におけるCSRの必要性が語られる時によく、高度経済成長期の公害問題を筆頭に、1960年代から1990年代にかけて多発した企業の不祥事、さらに2000年に起こった雪印集団食中毒事件、同じ年から2004年までの三菱自動車のリコール隠しなどが挙げられます。しかし、そうしたコンプライアンス(法令遵守)はもとより、そもそも企業に社会的責任が求められるのは必然的なことなのです。日本でも一定の歴史がありながら、本格的に企業が動いてこなかったのは怠慢としか言いようがありませんね」
インタビューの前に基本的な知識はある程度得てきたつもりだったが、林田さんの説明はわかりやすく、まるで大学の講義を受けているよう。CSR経営の重要性の解説だけで1時間強を費やしたこと、その時間があっという間に感じられたことが当時の取材ノートに記されている。が、取材記録を確認するまでもなく、当時の情景を昨日のことのように思い出す。
「まずはコンプライアンスと環境対応、そして社会貢献。この3つを重要な柱として活動内容に位置づけるべく取り組んでいますが、いずれはヨーロッパのCSR活動のように、地域や顧客、NGOまでも巻き込んで社会課題に取り組んでいかなければなりません」
CSRを担当するまで、経営企画部と広報部を行き来し、しゃべり慣れているようだったが、それも社内で活躍するために努力を重ねて修得した技だった。
「実は私はもともと商品企画が希望だったのですが……新人の頃に配属された時に能力を発揮できずに、バックオフィス部門に異動させられました。それだけに人一倍努力して、情報収集・伝達力やプレゼン、話術を磨いてきたつもりです。だから、社内でのCSR活動開始の情報をいち早くキャッチして、自ら志願して担当になったこのチャンスを、何としても生かしたいと思っているのです」
かしこまった話し方は変わらないものの、やや気持ちが昂ったのか、自身の志を語る頬に少し赤みが差したのを覚えている。