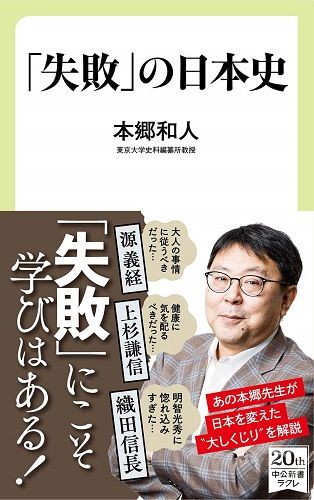「大政委任論」との関係
かつて農民一揆の鎮圧というと、大名権力は酸鼻を極めた手段を採ったと語られました。農民たちはまさに「なで切り」にされたような描写がありました。
いまはそうした事態は否定されています。苛烈な弾圧を行えば、大名もまた幕府から取り潰しなどの処罰を受けることが分かってきたのです。一揆の側も直ちに暴力に訴えるのではなく、まずは話し合いを行ったこと、農民の要求はある程度は受け入れられたことが指摘されています。
とはいえ、やはり異議を申し立てた首謀者たちは、打ち首などの極刑に処されるのを避けられませんでした。日本各地に「義民だれだれの顕彰碑」が残っていますが、仲間たちのために命を捨てて事に当たった彼らは、やはり尊敬すべき人たちですね。
それから「大政委任論」との関係も忘れてはなりません。
最後の将軍である徳川慶喜は大政を天皇に奉還したわけですが、では天皇はいつ将軍に大政を委任したのか。定説はまだないと思いますが、ぼくが説得力を感じるのは、天候不順から享保、天明の大飢饉が起きた1730~1780年ごろ、というものです。
将軍は政治を預かっているが「仁政」が実施されていないと「天」が怒り、天候が荒れ、飢饉が起きる。
この解釈を元に、将軍は仁政を行うことを使命として、「天」の代弁者である天皇から行政の権限を預かっているのだ、という思想が生まれてくるのだろうと思います。
大河ドラマ「べらぼう ~蔦重栄華乃夢噺(つたじゅうえいがのゆめばなし)〜」
【放送予定】2025年1月~
【作】森下佳子
【主演】横浜流星(蔦屋重三郎 役)
【制作統括】藤並英樹 【プロデューサー】石村将太、松田恭典 【演出】大原 拓、深川貴志
【放送予定】[総合]日曜 午後8時00分 / 再放送 翌週土曜 午後1時05分[BS・BSP4K]日曜 午後6時00分 [BSP4K]日曜 午後0時15分