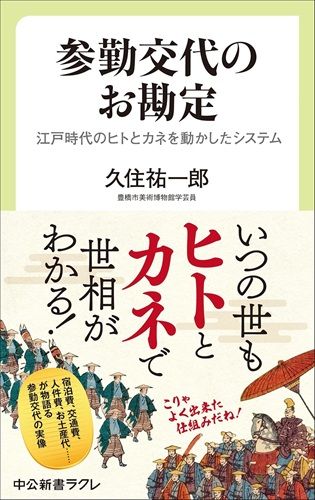関札が示す本陣の評価
現代では、旅行で宿泊するホテルを探す際に、予約サイトのクチコミを参考にする人は多いのではないだろうか。一方、江戸時代は、参勤交代のルートは決まっていたものの、先約が入っていたり、川留めなどで旅程が急遽変更になったりすることがあり、必ずしも毎回同じ宿場町を利用するわけではなかった。新発田藩の記録類の中には、現代のクチコミのように宿場町の良し悪しを記した道中記が複数残されている。
溝口景賢は御供の家臣たちのトップであったため、本陣に次ぐランクの脇本陣に泊まることが多かった。景賢も慶応元年(1865)の旅日記に宿場町や宿屋についてあれこれ評価を記している。部外者が見ることはない日記ということもあり、かなり率直な感想が綴られているが、これは次に信州通を利用して参勤交代をすることになった場合の参考にするためであったと思われる。
例えば、地蔵堂宿の宿屋は「極めて手狭で田舎の家」と辛めの評価、寺泊の名家五十嵐武兵衛宅は「一体古跡の風景に見ゆ」という上々の評価を付けている。
景賢は水回りにこだわりがあったようで、宿屋の風呂場やトイレについては次のような感想を記している。
片町宿の宿屋の風呂場は狭い上に見苦しい。新井宿の宿屋は焼失後の仮普請で手広ではあるが、風呂場は悪いので入浴はパスした。牟礼宿の本陣は手狭で「本陣の体にあらず」という有り様だが、脇本陣は新築で手広く風呂場やトイレまできれいであった。坂木宿の宿屋の風呂場は勝手口の方にあったので入浴はパスし、トイレも見苦しかった、といった具合である。
中山道に入ってからは利用者が多いためか、風呂・トイレともにきれいに保たれている宿場町が多かった。
若殿が宿泊した本陣で景賢が注目したのが関札である。関札とは、本陣利用者の名前・日付・利用形態などを記した木製または紙製の札で、宿場町の出入り口や本陣の前に掲げられた。矢代宿の本陣には、加賀藩主をはじめ大名の関札が数多く飾られていた。北国街道と中山道の分岐点である追分宿は利用者が多いため関札コレクションも豊富で、加賀・仙台・熊本・高田といった諸大名のものが多くあり、京都の公家たちの関札もあった。
これらはこれから使用するものではなく、使用済みの関札たちである。もちろん新発田藩主のものもあった。本来関札は宿泊や昼休が済んだら不要になるが、こうして過去の利用者の関札を実績として他の利用客に見せびらかすことで本陣の格を高め、利用客からの信頼度を増す効果があった。現代でも芸能人や著名人のサイン色紙を飾っている旅館があるが、その先駆けと言えるだろう。
関札がたくさんあるということは、それだけ多くの大名行列が通行するということの証左である。この時も加賀藩の行列とニアミスした。
4月29日、利根川水系の烏川にはたくさんの船を並べてその上に板を渡した「船橋」が架けられていた。これは江戸から上京する加賀藩主前田斉泰の通行に備えてのものであった。新発田藩の若殿一行は加賀藩の行列とのすれ違いを避けるため、間(あい)の宿の石神村の茶屋で休憩し、行列が通り過ぎるのを待った。
大名行列同士がすれ違う際は家格の違いにより対応が異なり、トラブルの元になってしまうため、通常はすれ違う可能性のある大名行列の情報に気を配り、今回のように家格が低い方が避けてかち合わないようにしていた。大名行列が街道ですれ違い、駕籠の戸を開けて大名同士が言葉を交わすということは、よほど仲の良い大名同士でなければ見られない光景だったのである。
※本稿は、『参勤交代のお勘定-江戸時代のヒトとカネを動かしたシステム』(中央公論新社)の一部を再編集したものです。
『参勤交代のお勘定-江戸時代のヒトとカネを動かしたシステム』(著:久住祐一郎/中央公論新社)
幕府が大名の力を削ぐための施策であったという理解は今は昔。
最新の研究や詳細な史料をもとに、参勤交代の多面的な姿を明らかにする。
『三河吉田藩・お国入り道中記』で、三河吉田藩という一つの藩をマニアックなまでに掘り下げた著者が、経済や文化に多大な影響をおよぼした参勤交代の、巨大で豊かな全体像に迫る。