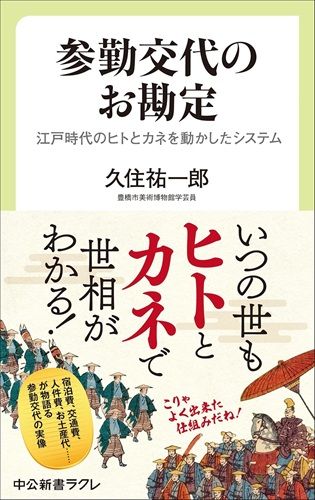移動するヒト・モノ・カネ
江戸時代は日本史上のそれ以前と比べてとにかく移動が盛んになった時代だった。その大きな要因の一つが参勤交代だったのである。全国各地に大名が配置されて城下町がつくられ、大名行列が行き来することで江戸と各地を結ぶ街道交通網が成立した。街道には宿場町が指定され、モノを運ぶための人足と馬が常備された。
モノの中には情報も含まれる。幕府が各宿駅に配置した継飛脚は、老中をはじめ幕府の要人のみが使える飛脚で、リレー形式で昼夜を問わず走り続け、江戸と京都を最速3日で届けた。
有名な「忠臣蔵」の中で、浅野内匠頭(たくみのかみ)が殿中で刃傷(にんじょう)におよんだことを知らせる早駕籠が江戸から赤穂(あこう)まで駆け抜ける場面があるが、約680キロメートルの道程を4日半で移動したとされる。無線や電話、インターネットもない時代に正確な情報をいかに早く手に入れるかというのは重要な問題であった。参勤交代は、その課題の解決にひと役買ったわけである。
陸上交通のインフラが整ったことで、経済的に余裕が生まれた一部の庶民が社寺参詣・湯治・物見遊山などの旅に出るようにもなった点も重要である。ヒトが動けばカネも動く。宿泊・食事・土産・消耗品など、旅先でお金を使う場面は多々あり、消費活動が活発になった。これは江戸時代の消費経済の発展に大きく影響している。
もちろん、山道や河川などの難所に関所、あるいは治安の問題など、旅をする上で現代とは比較にならないほど様々な障害や制約があった。だが、参勤交代制度の副次的効果として活発になったヒト・モノ・カネの移動は、江戸時代の社会に経済的・文化的な豊かさをもたらしたのである。
※本稿は、『参勤交代のお勘定-江戸時代のヒトとカネを動かしたシステム』(中央公論新社)の一部を再編集したものです。
『参勤交代のお勘定-江戸時代のヒトとカネを動かしたシステム』(著:久住祐一郎/中央公論新社)
幕府が大名の力を削ぐための施策であったという理解は今は昔。
最新の研究や詳細な史料をもとに、参勤交代の多面的な姿を明らかにする。
『三河吉田藩・お国入り道中記』で、三河吉田藩という一つの藩をマニアックなまでに掘り下げた著者が、経済や文化に多大な影響をおよぼした参勤交代の、巨大で豊かな全体像に迫る。