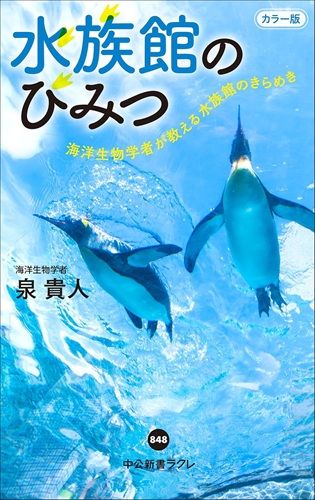ショー(パフォーマンス)――がんばった方が長生きする?
水族館のもう一つの大事な要素も(展示の一種なので)お伝えしておこう。それは、ショーの話だ。ちなみに、今はほとんどの園館でショーという言葉を使わず「パフォーマンス」という。「見世物ではなく演技だよ!」ということなのだろう(……大して変わらない気もするが)。
水族館の花形、イルカやアシカのショー。その歴史は意外と古く、少なくとも1950年代には江の島マリンランド(神奈川県、新江ノ島水族館の前身)でイルカショーが行われていたとされる。アシカに関しては、イルカとは違って動物園でも飼える都合、芸を見せるというスタンスのショーはもっと昔から行われていたらしい。
その後、全国に水族館がつくられるとともに、イルカ・アシカの飼育をする場所も増え、そのパフォーマンスも多岐にわたっていった。昔ながらのバンドウイルカ・カリフォルニアアシカだけでなく、昨今はセイウチ、アザラシ、シロイルカ(ベルーガ)、シャチに至るまでがショーをする。水族館ごとに独自のプログラムを設けており、最近は音響やプロジェクションマッピングも駆使した豪勢なショーを展開する園館もある。
で、またもや社会的な話になってしまうんだけど、大体この手の話題では「ショーで酷使されてかわいそう!」という話が出てくる。イルカやアシカに話を聞けないから、奴らがどう思っているのかは正直、分からないと前置きした上で……実は、このショーは、健康維持の観点から重要だったりする。
ほら、海では魚や獲物を追いかけたり、天敵から逃げたりするために、かなりの運動を要する。一方、水族館では天敵はいないし、餌も飼育員さんから貰えるので、自然界ほど運動する必要がない。
しかし、人間界にも生活習慣病という言葉がある通り、動物たちも野生下の体形を維持するのが難しく、健康を害するんだよね。だから、日々の運動をさせてやるために、ショーは有効なのだ。ストレスを感じさせないように、なるべく奴らの遊びの延長としてプログラムを組んでいるらしい。パフォーマンスである程度遊ばせてやった方が、長生きするという説もあるそうだ。
※本稿は、『水族館のひみつ-海洋生物学者が教える水族館のきらめき』(中央公論新社)の一部を再編集したものです。
『水族館のひみつ-海洋生物学者が教える水族館のきらめき』(著:泉貴人/中央公論新社)
水族館は、発見の宝庫だ。
日本全国の水族館の「表」も「裏」も、「酸い」も「甘い」も知り尽くした海洋生物学者が、水族館の真の魅力を解説する。
水族館が100倍楽しくなること請け合いだ。