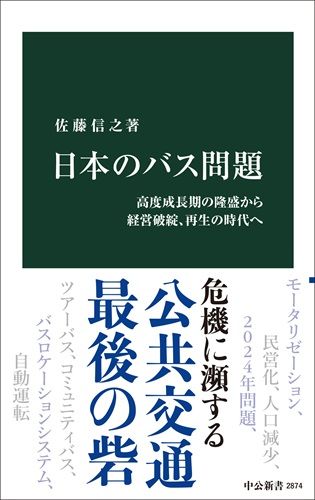印西市のコミュニティバス
武蔵野市の成功を受けて、各地でコミュニティバスの導入が進んだ。著者もコミュニティバスの運営に関わったことがある。それは千葉県印西市のコミュニティバスで、運行会社を競争入札で決定した。入札者が入札したのは市の補助金額に対してで、バス運行の経験などを勘案して市の負担額が少なくなる事業者に決定した。結局は、並行路線や近隣で路線バスを運行する事業者が、他社の参入を抑えるために低い額で入札する傾向があった。
印西市の場合も100円均一運賃で、さらに市役所等で無料で乗り継ぎできることから、乗り継ぎと申し出れば復路が実質的に無料で利用できることなどの制度的な問題もあり、落札金額の補助金では採算がとれていないのが現実である。さらに一部路線バスと競合する場合、路線バスとの運賃差が大きいためにコミュニティバスへ旅客が流れて、路線バスの維持が難しくなっている。
武蔵野市のような大都市近郊の需要の旺盛な地域で成功した低価格のコミュニティバスを、需要が限定され、さらに路線バスと競合する地域にそのままの形で導入するのは無理がある。またムーバスの場合、もともと短距離の利用者を対象とし、片道の所要時間はせいぜい10分程度であるのに対して、印西市の場合は循環路線で1周1時間ほど、平均的に20〜30分程度乗車しており、想定される利用形態がムーバスとは違うのに同じ100円という低価格を設定したのも無理があるといえるかもしれない。
むしろ運賃は200円として対象を限定して割引措置をきめ細かく設定し、同じ割引を並行路線バスでも利用できるようにして、コミュニティバスと並行する民営バスとのサービスの格差を縮めて、一般路線バスの経営を持続可能とする考えもあってよかったのではないかと思う。
※本稿は、『日本のバス問題-高度成長期の隆盛から経営破綻、再生の時代へ』(中央公論新社)の一部を再編集したものです。
『日本のバス問題-高度成長期の隆盛から経営破綻、再生の時代へ』(著:佐藤信之/中央公論新社)
本書は日本におけるバスの誕生に始まり、戦後のモータリゼーションとその対抗策として生まれた様々なサービスを解説する。
さらに既存バス会社の保護から規制緩和へという流れと、新たに生まれた独創的なバス会社も紹介。
日本のバス事業の課題と将来を展望する。