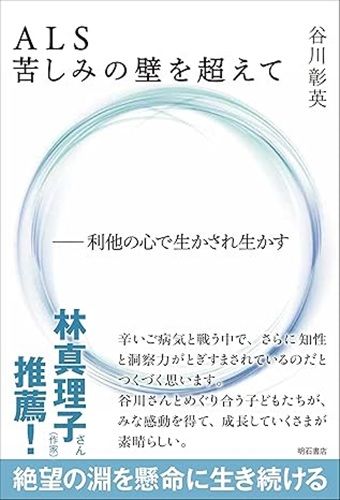本を書くための壮絶な戦い
私の日々の執筆活動を支えてくれているのは、伝の心という障害者の意思疎通用に開発されたパソコンです。対社会の交信は100パーセントこの伝の心で行っています。まさに命綱なのです。20世紀最大の発明はコンピュータだと言われますが、よくぞ開発してくれたと人類に感謝するのみです。
伝の心は障害者の意思疎通のためのパソコンと言いましたが、私は通常のパソコンの代わりとして使っています。手は動きませんが、腕にかすかに残る力で特殊なマウスを押して操作します。文字を打つにも通常のパソコンの数十倍の手間暇がかかりますが、辛抱強くやりぬけば本を書くこともできます。ただ、それは壮絶な戦いです。
毎日10時間ほど伝の心に向かっていますが、いつも恐怖に思っているのは、パソコンの不具合です。機械ですから不具合が生じるのは避けられませんが、パソコンが機能しなくなった時の絶望感は想像を絶するものがあります。
※本稿は、『ALS 苦しみの壁を超えて――利他の心で生かされ生かす』(明石書店)の一部を再編集したものです。
『ALS 苦しみの壁を超えて――利他の心で生かされ生かす』(著:谷川彰英/明石書店)
2018年にALS(筋萎縮性側索硬化症)を発症し、苦悩と絶望に追い込まれながらも、できることは必ずあるとあきらめずに生きてきた6年間、難病当事者としての著者の想いはどのように変わったのか、そして多くの人との出会いにより何を見つけたのか。
極限の不自由さと引きかえに手にした利他の心に生かされる自分、そして同時に支えてくれる人たちや苦しみの只中にいる人たちを生かしている自分に気づくまでの軌跡を赤裸々に綴る。
2025年4月、谷川彰英さんの妻、憲子さんが死去しました。以下に谷川さんの弔辞を掲載します。
本日はご多用のところ、妻憲子の会葬にご参列いただきありがとうございました。突然の訃報に皆様から一様に「言葉もありません」とのお悔やみの言葉をいただきました。
前日の2日は東京書籍の役員の方がお見えになり歓談したばかりでした、私はその打ち合わせの原稿を打っていたために昼食が取れず、妻はそれをおもんぱかって8時半ごろ私の部屋に来て、「お腹すいてない? もう寝るね」と、いつになく優しく声をかけてくれました。それが最後の言葉になりました。私の胸に深く深く刻まれた愛の言葉でした。
翌朝心臓の発作を起こし、千葉大附属病院に搬送されましたが、8:57 に息を引き取ったとのことでした。
「憲子、起きろ! 目を開けてくれ!」
帰宅した憲子に心で呼びかけました。すぐにでも目を開けそうな安らかな顔立ちでした。それは好きだった京都の永観堂の「みかえり阿弥陀」さながらの美しさでした。
憲子との出会いは、私が学部時代に都内の主要大学に呼びかけて組織した「教育学を学ぶ会」でした。それ以来ほぼ60年間寄り添ってきましたが、陰に陽に私の仕事・活動を支えてくれました。「ありがとう!」を100万遍叫んでも足りません。
私は新しい組織を作るのが得意で、数えるのが難しいほどの会を作って運営してきましたが、憲子は愚痴をこぼすこともなく、事務局の仕事をこなしてくれました。口の悪い友人は、「谷川の業績は8割方奥さんの力だ」と言っています。その通りかもしれません。
憲子にしてあげられたことはあまりありませんでしたが、たった一つだけ憲子のためにしたことがあります。それは子育てが終わった 40 代の後半の憲子に大学院進学を勧めたことです。筑波大学の小林重雄先生のもとで障害児教育について2年間学ばせていただきました。本人にとっては最高に楽しく充実していたようで、その後よく「大学院進学が私の人生を変えた」と言っていました。
それが機縁で、看護学校の講師の他千葉県の発達障害センターの相談員などを務めていました。「コバ研」並びに関係の皆様には、生前に賜ったご厚情に心より感謝申し上げます。
憲子を死に追いやったのは、ALSと闘う私の介護疲れによるストレスではなかったかと思います。ALSを発症して7年、ALSを宣告されて6年が経ちました。その間1日も休まず、私のケアに力を尽くしてくれました。私は憲子に謝罪すべきなのです。
しかし、ALSと闘う身の私にはサポートすることは不可能でした。運命を呪うのみです。
ALSに倒れる前は、2 人で好きなところに旅をして宿で地酒を酌み交わすことを夢見ていたのですが、一度も果たすことはできませんでした。それだけが心残りです。申し訳ない思いで一杯です。
2,3年前にひざの手術をして以来、歩行が困難になっていました。とりわけ昨年の秋頃から顕著になり、最後は家の中を歩くのもやっとという状態でした。
加えて、精神的にも追い詰められていったように見えました。年が明けてから「私の方が先に逝くかもしれない」と口走るようになりました。その時点で来るべき運命を感じ取っていたのかもしれません。
憲子はよく私に「私の気持なんかちっともわかっていないんだから」と言うようになりました。全ての咎(とが)は私が負います。ですが、最大の原因は私が発声できないことにありました。しゃべれないというハンディの残酷さを身をもって体験しました。しゃべることさえできたら憲子の心に寄り添えたのでないかと思うと、胸を締めつけられる思いです。
昔聴いたある心理学者の講演を思い起こしました。それによると、肉体は滅んでも遺伝子は生き続けるので、死んだことにならないとのことでした。憲子は口癖のように、「良い息子と良い嫁と4人の孫に恵まれて幸せだ」と言っていました。この6月には、ピアノ教室の発表会で、今年小2になる海音と連弾すると言ってピアノの練習を再開した矢先のことでした。
憲子の魂は間違いなく孫たちに生き続けます。残された私たちはその成長を見守っていきます。
憲子は別れの言葉もなく、特別列車に乗って旅立っていきました。それは胸を引き裂かれるような悲しい出来事ですが、私は憲子に再会できると信じています。やがて私も旅立ちますが、特急列車で追いかけます。憲子はどこかの駅のホームでいつもの笑顔で迎えてくれることでしょう。その時改めて感謝の気持を伝えます。
司令塔を失った今の私は糸の切れた凧同然の状態です。どういう境遇になるのかもわかりません。でも負けません。実は年明けからALS宣告後10冊目に当たる『ALS 生きる勇気の波紋』の執筆に取りかかったばかりの出来事でした。憲子からもらった愛に報いるために、本書は必ず書き上げます。そして再会の駅のホームで手渡してきます。
勝手な思いを申し述べさせていただきました。改めて本日の会葬にご参列いただいたことに心より感謝申し上げます。これまで親しくお付き合いいただいた皆様にお会いできて、本人もきっと喜んでいると思います。最後に皆様のご健勝をお祈り申し上げ、お礼の挨拶とさせていただきます。ありがとうございました。
2025年4月8日
喪主 谷川彰英