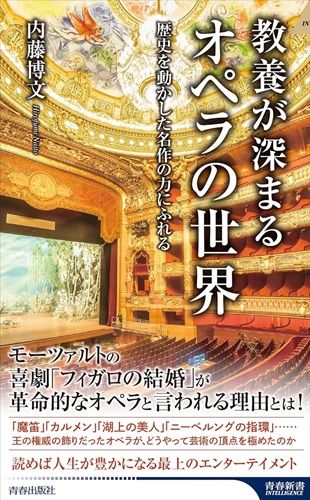近代の萌芽
「フィガロの結婚」は、市井の人フィガロが伯爵をやり込めるという物語自体に、革命と下剋上がある。これも近代の萌芽だが、もう一つの近代へのステップは登場人物の俗物性にある。伯爵はデタラメな人間であり、伯爵夫人も小姓のケルビーノの求愛によろめくのだから、軽いといえば軽い。
これまでの社会通念では伯爵には高い道徳性があるかのように思われてきたが、その道徳性のなさ、俗人ぶりは市井の人と変わらないのだ。市井の人であるケルビーノにしろ女好きの小僧、主人公のフィガロは好漢ではあるが、ある意味、その場しのぎの男である。そこには、崇高さのかけらもない。
彼ら登場人物の俗人ぶりもまた、近代なのである。近代というのは、相対化の時代である。それまで絶対に正しいと思われていた人の「絶対的な正しさ」がものの見事に崩れ、俗人と同様になる。一方、俗人にもまた正義があるのが近代だ。
「フィガロの結婚」は、音楽の面でもストーリーの面でも革命的なオペラであり、近代を告げるという点で、フランス革命に先んじていたのだ。
※本稿は、『教養が深まるオペラの世界』(青春出版社)の一部を再編集したものです。
『教養が深まるオペラの世界』(著:内藤博文/青春出版社)
ヨーロッパ最高の娯楽であり教養であるオペラとはどういうものか?
日本人に人気の『フィガロの結婚』をはじめ、オペラの主要作品を、その背景にある世界史の流れも踏まえて、わかりやすく解説。
オペラ初心者でも、オペラ愛好者であっても、その面白さ、奥深さを堪能できる一冊。