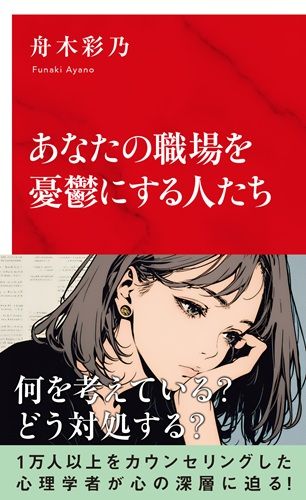ASDが疑われる上司への対応法
このような上司にあたった場合、部下はどう振る舞えばよいでしょうか。
当然ながら、発達障害の傾向があるかどうか、上司に直接確認するわけにはいきませんが、部下を憂鬱にさせる数々の言動には、発達障害グレーゾーンにみられる特性が関係していると思われます。このような場合、発達障害グレーゾーンの知識をもとにして、適切な対応法を部署で共有すれば、うまくいけば双方にとって働きやすくなります。
ASDが疑われる上司への対応法について、いくつかのポイントを紹介します。
●発達障害グレーゾーンやASD特性について、正しく理解しましょう。
→上司が部下を傷つけようとしたり、見下したりして発言しているわけではないことがわかり、部下自身のストレスマネジメントにもつながります。
●報告するときは、結論から述べるようにしましょう。
→背景や理由などから説明しているうちに、混乱させたり、苛立たせたりする場合があります。
●どこまでやれば仕事は完成したといえるのか、事前にすり合わせをしておきましょう。
→求められている内容や費やしてよい時間などについて、お互いの認識にギャップがあることが少なくないため、それを埋める必要があります。
●上司の言い方に傷ついた場合は、「私は、**さんの××という言葉に傷つきました」と伝えましょう。
→ASD特性がある人は悪気なく言っている場合がほとんどですが、Iメッセージなどの技法を使って相手に自分の気持ちを伝えることは、自分の心を守るうえで有効です(自分を主語にして気持ちを伝える技法をIメッセージといいます)。
本事例では、カウンセラーが上司と部下の双方から話を聴く機会があったことで、それぞれが留意すべき点を伝えることができました。このようなケースに遭遇した場合、上司と対等に話せる人や、コミュニケーションに慣れている人に間に入ってもらうなど、ワンクッション入れる工夫も必要でしょう。
その後、高山さんは自身の特性を人事部と共有し、管理職から外れて研究職として働きたいと申し出る決心をしたようです。
※本稿は、『あなたの職場を憂鬱にする人たち』(集英社インターナショナル)の一部を再編集したものです。
『あなたの職場を憂鬱にする人たち』(著:舟木彩乃/集英社インターナショナル)
あなたの職場には「この人さえいなければ、もっとストレスなく働けるのに」という人はいませんか。
問題があるのは、上司、部下、それとも同僚? ひょっとしたら自分自身なのかも?
官公庁や総合商社、中小零細企業、研究所、小売業まで、さまざまな職場で1万人以上のカウンセリングをしてきた心理学者が、豊富な実例を挙げ、問題の根本を探り、具体的な解決策を提案していきます。