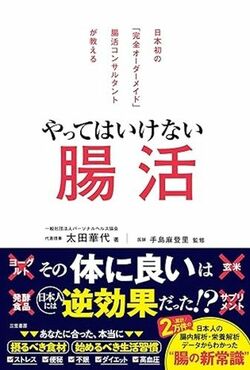「よく噛んで食べなさい」は、科学的に正しかった
「食べるもの」が変わることで、それを吸収する腸の環境が変わるのはある意味当然のことですが、実はこの「食の欧米化」は、もう一つ大きな“副作用”を私たちにもたらしました。
それは、「噛む回数の減少」と、それにともなう「顎の退化」です。
子どもの頃、親から「よく噛んで食べなさい」と言われた経験はないでしょうか。
実際よく噛むことは本当に大事で、特に腸内環境を整えるうえでは不可欠の行為です。
あまり噛まずに飲み込んでしまえば、消化不良を起こし、直接的に腸内環境が悪くなります。また、噛まないことで唾液の分泌が少なくなれば、口腔内細菌が増えやすくなり、それが腸内に定着してしまう可能性も高くなります。
もともと、玄米や雑穀を主に食べていた時代は、「よく噛む」のは当たり前のことでした。当時は、食事中にテレビやスマホを見たりすることもありませんでしたから、「食べる」という行為に意識を集中しやすく、なおさらしっかり噛むことができたはずです。それゆえ、当時の日本人は強い顎と歯を持っていました。
しかし、普段から柔らかいものを好んで食べ、テレビやスマホを見ながら食事をするようになった現代人は、この「噛む力」がどんどん弱くなっています。
そのうえ、「タイパ」を重視してなのか、食事になるべく時間をかけず、必要以上に「早食い」をする人も増えてきています。
実際に、子どもたちの顎が小さくなり、歯並びが乱れ、歯の本数も少なくなっていると、多くの歯科医師たちが指摘しています。