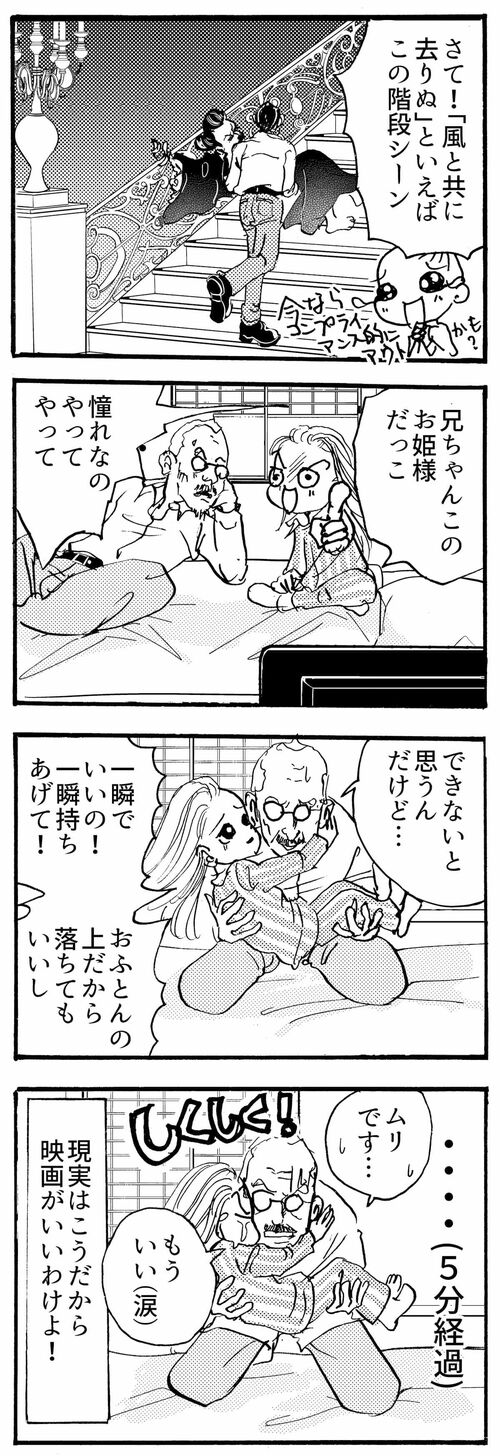文学的な評価
さて、原作はM.ミッチェルのベストセラー小説だが、文学的な評価はあまり高くないと聞く。ネットで検索すると、「あくまで白人の視点からのみ描かれ、奴隷制度を正当化している」「白人至上主義のKKK団を肯定している」などが批判の理由のようだ。
実際、KKK団の黒人差別は酷いものだったから、批判は理解できる。南北戦争で多くの奴隷が解放されたことも肯定されて当然だ。しかし、コストのかからない労働力を当然のものとして受け継いできた特権階級の人々の思いを正直に描いた点は、大いに評価されるべきだろう。歴史の出来事は、立ち会うものの立場によって評価が分かれるのだから(被支配者目線で描かれた奴隷制度の悲惨さについては、今後『ROOTS』という作品を紹介予定)。
ちなみに、スカーレットら南部の上流階級を「貴族」と評する解説を散見するが、アメリカに「貴族」は存在しない。スカーレットはあくまで裕福なる農場主の娘。だからあの奔放なキャラクターが成立する。レットとの豪華新婚旅行で食事に食らいつく野性、品のなさ、TPOをわきまえない派手すぎる衣装は、決して「貴族」のものではない。
しかし、そんな「やりすぎキャラクター」がまた魅力的なのだ。スカーレットもレット・バトラーも「いい人」とはとてもいえないが、振る舞いがいちいち痛快。悪い奴だと分っているのに、好きにならずにいられない。
フィクションの人物でこれほど存在感を示すキャラクターはそういないだろう。彼らはジェームズ・ボンドやレイア姫、あるいはドン・コルレオーネさながらに私たちの心に入り込み、トラウマのように「実在」する。メラニーや街の女のベル・ワットリングしかり、黒人奴隷のマミー、嘘ばかりつくプリシー、スカーレットを愛するのに報われないチャールズやフランク、最後まで煮え切らなかったアシュレー…。誰もが強い個性を持ち、その後ろの人生が見え隠れするように、愛をもって丁寧に描かれている。だからこの映画は、私たちの心を打つのだろう。