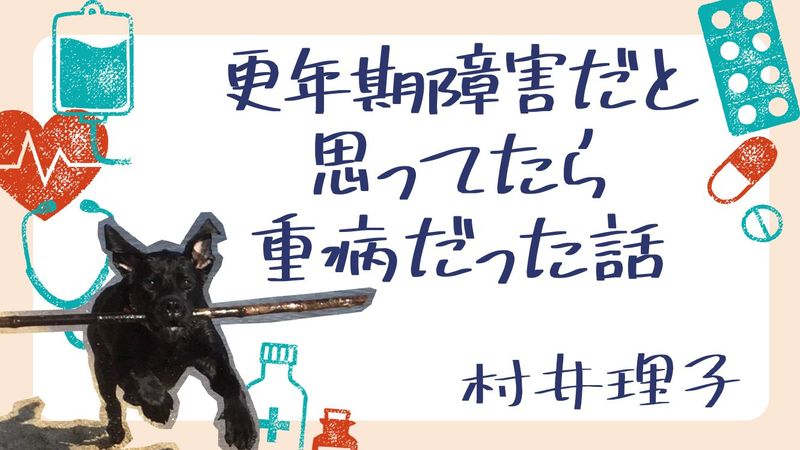胸には心臓モニターのパッドがべたべたと…
突然体調を崩し、病院に運ばれ、心臓に重大な疾患があるようなので緊急入院して頂きますと宣告されたわりには、私はとても落ちついた気持ちでベッドに横たわっていた。今考えてみれば、これはいわゆる、「闘争・逃走反応」だったのではないかと思う。強い恐怖を抱いたり、危機に陥ったときの人間の反応で、たぶん私の脳内ではアドレナリンが大量に放出されていたのではないだろうか。そう思えるほど、私はのほほんとした気分で病院のベッドに横たわっていた。胸には心臓モニターのパッドがべたべたと貼り付けられ、指先にはパルスオキシメーター(血中の酸素飽和度を測定する装置)、腕には数本の点滴の針が刺さっていた。ベッドの横に真っ青な顔で座っている夫に、へらへらと笑いながら、「心臓だってさ」と軽口を叩いた。
「さっき、心臓のエコー検査したやん? あの検査技師の人、『弁膜症って言われたことありますか?』って言ってはったんよ。これたぶん、弁膜症やわ……ハハハ、ありえないよね、今さら弁膜症とか! 子どものときに手術したってのに!」
笑っている私に対して夫は無言だった。
「ねえ、子どもたち、どうしよう。登校はいいけど、困るのは下校だよね。誰かが家にいないと、どうなるんだろ。お隣さんに頼めるかな……いや、たしか彼女、フルタイムで仕事してたな……」
私は当時小学5年生だった息子たちのことをひっきりなしに心配していた。それから、飼いはじめたばかりの1歳のラブラドール・レトリバーのハリーのことが気がかりでならなかった。ハリーは、体は大きいものの、まだまだ子犬だった。1匹で留守番など絶対に無理な状態で、子どもが学校に、そして夫が会社に行ったあとの時間を、どうやって過ごすのかが大きな問題だった。当時、ハリーを5分でも留守番させると、家のなかは空き巣にでも荒らされたかのような状態になった。それだけではなく、飼い主がいなくなることでパニックになるハリーが、外に向かって延々と大声で遠吠えをするので、ご近所中の迷惑になったこともあったのだ。夫の両親に頼むことはできるけれど……いやいやいや、無理だ。ハリーはまだ1歳だけれど、その力たるや大柄な夫でも振り回されるほどだった。まだ精神的に幼く、その破壊力をコントロールできないハリーを老夫婦に任せるなんて、あまりにも危険だった。