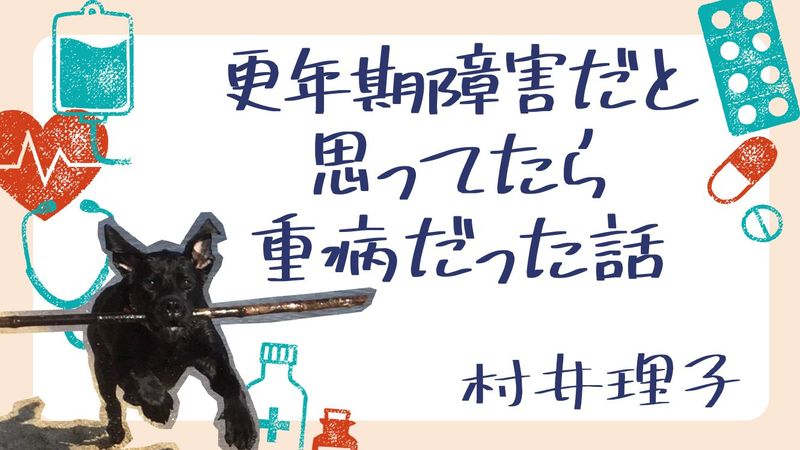第1回が配信されるやいなや、大きな話題になった翻訳家・村井理子さんの隔週連載「更年期障害だと思ってたら重病だった話」。47歳の時に心臓に起きた異変。心不全という言葉が、病人の心に鋭く突き刺さる。追い打ちをかけるように、隣のベテラン患者から暴言を吐かれ、村井さんはナースステーションに「個室に移りたい」と伝えに行って……。『兄の終い』の著者が送る闘病エッセイ第3回。
涙がじわじわとわいてくる
大股で歩いて暗い病室に戻った私は、早速、荷物をまとめはじめた。
横のベテラン患者のベッドには、娘さんがお見舞いにやってきていた。私とそう年齢が変わらない人だろう。それは、うしろ姿から、声の感じから、推測できた。なんとなく嫌な気持ちになった。同じぐらいの年齢の女性だというのに、かたや私は重病人、彼女はとても健康そうだ。私が戻ると、2人でなにやら小さな声で話をしはじめた。「…しんぞう……」というささやきが漏れ聞こえてきた。涙がじわじわとわいてくるのがわかった。
多くの荷物は持ち込んでいなかったが、簡単な洗面道具や数冊の本、ケータイといった細々としたものは持っていた。すべて、急いでトートバッグに詰め込んだ。個室の準備がいつになるかはわからなかったが、いつでも移動できるように、準備万端整えていないと落ちつくことができなかった。荷物を入れたバッグを胸元に握りしめ、薄暗い自分のスペースの真ん中の、古ぼけたベッドに体を固くしたまま横たわった。私は、初めての場所が極端に苦手で、夜は一睡もすることが出来ないだろうと確信していた。
目の前にあるテレビが置かれた棚は、経年劣化でプラスチック部品の色が変わっていた。隅にはうっすらとほこりがたまっている。思わず目をそらした。暗くて狭いスペースを仕切る緑色のカーテンは、手垢で薄汚れている。天井には、よく見るタイプの白い石膏ボードがびっしり貼られていた。その石膏ボードに刻まれている、規則的なようで不規則な黒い模様をじっと見つめながら、私は、「ふみちゃん」のことを思い出していた。