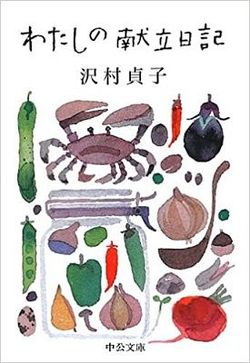「今日さまに申し訳ないからさ」
半世紀が過ぎてなお、日々恬淡と綴られる個人の献立の記録がとてもたいせつなものとして胸に響くのはなぜだろう。それは、日本人の身の丈がここにあるからではないか。身の丈に合った暮らし、ほどのよさ。沢村貞子は終生を通じてその意味を考え抜いて生きてきたひとである。自分の身の丈に合った暮らしは、生活思想の実践でもあったともいえる。その土台を築いたのは、生まれ育った浅草の庶民の生活であり、働きづめだった母の姿。
沢村貞子は明治四十一年、東京浅草に生まれた。父は狂言の座付き作者、竹芝傳蔵。母マツはそれこそ身を粉にして夫に滅私奉公した。芝居のことしか眼中になく、玄人の女たちにちやほやされた浮気者の夫を支える人生を送った母の姿は、惚れていたとはいえ、女として報われていたとは言いづらかった。四人兄弟の次女として貞子が生まれたとき、父がつぶやいたのは「ちぇっ、女か」。「自分のこどもはみな役者にする」のが悲願だったから、父の執念に応えるようにしてこどもたちは役者になった。兄はのちの四代目澤村國太郎、弟は加東大介である。お貞ちゃんと呼ばれて育った貞子は、六歳ごろから長唄や踊りの稽古に通いはじめ、家では母に厳しく家事を仕込まれ、すでに尋常小学校一年で夕飯のしたくをこなしていた。
大正十年、浅草七軒町東京府立第一高等女学校入学。家庭教師をしながらみずから月謝と本代を稼ぎ、昭和元年、教師の夢を抱いて日本女子大学師範家政学部に入学する。二十歳のとき、築地小劇場の女優、山本安英に「新劇の道を目指したい」と手紙を送って女優への第一歩を踏みだす。ちょうど兄は女形として人気がでて映画界へ引き抜かれ、弟も真剣に役者に取り組みはじめた時期だったから、一家の熱気は女優志願の追い風となったに違いない。こうして女優ひと筋に生きはじめるまでの二十年間、「今日さまに申し訳ないからさ」が口ぐせだった働き者の母によって、生活者としての気概を骨身に叩きこませながら育った。