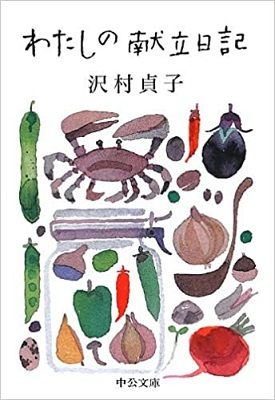きっぱりと圧を込めた濃い筆跡
じつは献立日記にはその先があった。このたびわたしは、献立日記をはじめ沢村貞子さんの遺品のいっさいを預かる元マネージャー、山崎洋子さんのご厚意によって、献立日記のその後に出逢うことになった。三十六冊めの献立日記がひっそりと終わりを告げたあと、二年後の平成六年にしたためられた日記帳のなかに、それは見つかった。
臙脂色のビニール装、市販の小型の日記帳の表紙に金色の型押しで「DIARY 1994」。めくると、見開き二ページが四日分の仕様になっている。そこにほんの数行ずつ、ボールペンでさらりと書かれた筆跡。かつての献立日記は、数行の日記のあとに書き添えるかっこうで、ふたたび現れる。平成六年、八十六歳。
○天麩羅(車えび、はぜ、しいたけ、さつま芋、いんげん)
○きんとん
○ほうれん草としらすの酢のもの
○おみおつけ(あさり)
○鯛のうすづくり
○天ぷらの残りの煮つけ
○春菊のごまよごし
○栗きんとん
○とろろ汁
かつて二十六年間の習慣が不意によみがえってきたのだろうか。それとも、年頭に当たって生きる元気を振り絞ろうとしたのだろうか。しかし、日記には歯の痛みのつらさがしきりに訴えられており、復活した献立日記は一月五日からほんのいっとき八日間のみ、一月十二日で終わっている。と同時に日記そのものも、何か月間もぷつりと途切れる。不意に再開するのは六月二十日、夫が体調を崩して市民病院へ診察を受けに行った日。こうして、かろうじて息を継ぎながら日記は切れ切れに続くが、一か月後の七月十七日、「恭彦死亡」とみずから記す。目の前の現実を自分に強く言い聞かせるかのような、きっぱりと圧を込めた濃い筆跡。その数日後から、日記はもう二度と開かれることはなかった。世を去るのは、それから二年後のことである。
献立日記は、沢村貞子にとって、自分の人生を全うするための心棒であった。それは、脇役女優として懸命に働き、たいせつにした夫婦の暮らしを守り通すための盾であったかもしれない。だからこそ、恬淡と綴られ続けた献立日記はぴんと背筋を伸ばした気の張りを湛えている。それは、沢村貞子の生きかたそのものである。