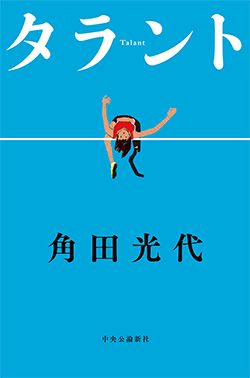ほうらい家は朝八時にオープンする。人気が出はじめたのはみのりが中学に上がってからで、このごろでは七時半にはもう店の前に行列ができている。祖母の笛子(ふえこ)が引退した後は伯父の克宏が店を継ぎ、七十近いのにまだ厨房(ちゅうぼう)に立っている。克宏の長男である嘉樹が補佐役、伯母の容子とみのりの母が天ぷらや稲荷(いなり)寿司といったサブメニュウを作り、アルバイトの子数人が洗いものを担当している。引退した祖母は、店の、客がうどんや天ぷらを受け取るカウンターのいちばん端に椅子(いす)を置き、まるで置物みたいに座っている。常連たちとおしゃべりをするためだ。見知った顔がなければそこに座ったままテレビを見つめて微動だにしないので、人形だと思った観光客がいたらしい。記念写真を撮ろうとして祖母の肩に手をまわし、その感触が人形ではないので、「ヒッ生きてる!」と叫んだと、ずいぶん前の正月に嘉樹が笑いながら話していた。
みのりはジャケットを羽織って家を出、祖父母の家に向かう。「おはよう」と声を掛けると、「みのりか」奥から祖母の声がする。玄関を上がり、茶の間に向かうと祖母が食卓でお茶を飲んでいる。年末年始に帰ったときと何も変わっていないように見える。「これ、まんじゅう、ありがとうな。お茶、飲むんな」立とうとする祖母を制し、食器棚から湯飲みを出して、食卓に載った急須のお茶を注(そそ)ぐ。祖母の向かいに座ってすすり、
「あいかわらず元気そうやな」とみのりは言う。昨日と同じ大きな音量でテレビがついている。

「腰が痛とうてかなわん」
「じいちゃんはもうじき、施設に入るんな?」みのりは訊いた。
「そやなあ、ほらうちは腰があれだから、難儀やけん、センターならあの人も好きなときに風呂に入れてもらえるやろうし、なんたってプロやから、センターの人たちは。今はほれ、あれなの、容子さんとタマだけじゃあれやから、サービスの人がきてくれとるけん、それだって、二週間に一回やな。トイレもな、まあ慣れとるけど不便は不便やな。それにここにおったら、寝とるかテレビを見とるだけや。まあ前からそんなもんやけど」と祖母は、みのり相手にというよりもテーブルに話しかけるように一点を見つめてとうとうとしゃべる。センターというのは介護施設のことでサービスというのは訪問介護サービスだろうとみのりは思いながら、相づちを打つ。
「ああ、もう店の時間かな? 今朝はな、とこちゃんが孫連れてくる言うとったから」よっこいしょ、と食卓に両手をついて祖母は立ち上がり、「あんたどうするんな、いっしょにいく?」
「ううん、じいちゃんに挨拶(あいさつ)して、すぐ出る」「寝とるよ」祖母は言い残して暗い廊下をゆっくりと歩いていく。磨(す)りガラスのはめこまれた玄関の引き戸が四角く発光している。祖母のうしろ姿がその光に吸いこまれるようにして戸の向こうに消えるのを見送って、みのりは祖父の部屋にいく。
「おはよう」と言いながらのぞくと、祖父はベッドに横になり、薄く口を開いて眠っている。レースのカーテンが日射しを吸いこんで光っている。古い和箪笥(わだんす)が壁にくっつけて置かれていて、その前に車椅子が畳んで置いてある。その下に、もうずいぶん装着していない義足が投げ出されたように放置されている。薄い夏掛け布団は祖父の呼吸に合わせてちいさく上下している。視線をずらすと、下半身のあたりで布団は不自然にぺったんこだ。祖父には左足がない。膝の上で切断されている。それで戦争から生きて帰ってこられたのだと祖母が言うのを、みのりは幼いころに聞いた。ただでさえ無口な祖父は戦争のこととなるとまったく話さないから、真偽のほどはわからない。
みのりは床に落ちているシャツを拾い上げて畳もうとして、何かが落ちたことに気づく。封筒だった。かがんで手に取ると、多田清美さま、と丸っこい文字で書いてある。切手はいわさきちひろで、消印は東京である。祖父と、その丸文字の癖が残る字が不釣り合いで、みのりは思わず封筒をひっくり返して差出人を確認する。名字はなく、ただ「涼花(りょうか)」とある。風俗店に勤める若い女性からの手紙だろうかとみのりは一瞬思うが、九十を過ぎた老人が、まさかひとりでそんな店まで通うはずがない。
つづきは書籍でお楽しみください