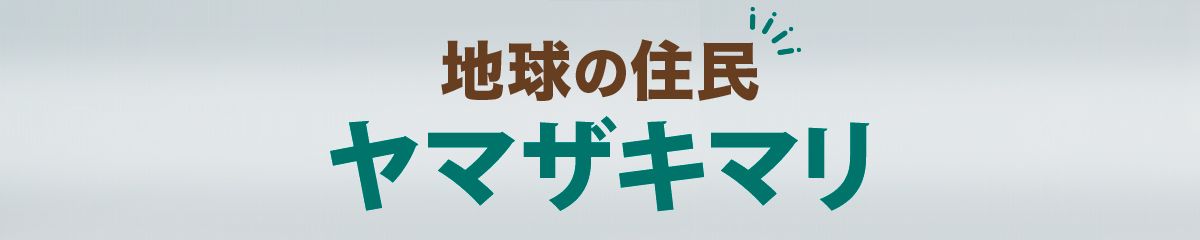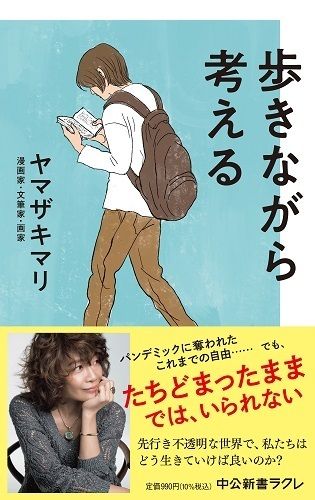トイレットペーパーと人々の意固地
ちなみにイスラム圏では、用を足したら左手を使ってトイレの脇にある蛇口につながったホースやバケツに貯めてある水で洗い、紙は使わない、という習慣が今でも続いているが、西暦800年代に中国を旅したアラビア人の手記によると、当時の中国人はすでにトイレで紙を使用しており、アラビアの旅人はそれを不潔な行為と捉えたそうだ。
しかし、シリアで暮らしていた頃、公共施設のトイレには水も紙も備えてあった。水で洗った後は紙の出番になるということだろう。トイレットペーパーの侵食は今やイスラム圏にも及んでいる。
そう考えると、ホモ・サピエンスがこれまでに利便性と快適性を追求してきたなかで、トイレットペーパーは文明的生活の維持に対する人々の意固地を象徴するものに見えてくる。
我が家のトイレットペーパーを切らしていることに気がついた勢いでこんな考察を綴ってしまった。買ってきます。
『歩きながら考える』(著:ヤマザキマリ/中公新書ラクレ)
パンデミック下、日本に長期滞在することになった「旅する漫画家」ヤマザキマリ。思いがけなく移動の自由を奪われた日々の中で思索を重ね、様々な気づきや発見があった。「日本らしさ」とは何か? 倫理の異なる集団同士の争いを回避するためには? そして私たちは、この先行き不透明な世界をどう生きていけば良いのか? 自分の頭で考えるための知恵とユーモアがつまった1冊。たちどまったままではいられない。新たな歩みを始めよう!