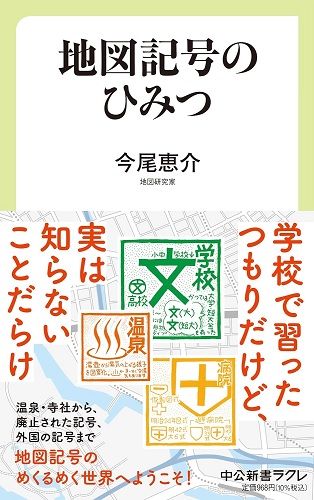湯気のゆらぎの向き
温泉記号を取り上げたのは『中央公論』での連載第1回であったが、そこで私が描いた冒頭の温泉記号のイラストについて専門家の方からご指摘をいただいた。
湯気のゆらぎの向きが違うのだという。
国土地理院の温泉記号の湯気は「平成14年地形図図式」で直線から逆S字形に揺らぐ形に改められたが、直後にJIS規格に合わせて変更、翌15年発行の地形図からS字形になったことを私が知らなかったためだ。
もちろん温泉マークに法的拘束力はないので、「私が描く地図ではこれが温泉記号」と勝手に宣言しても問題ないのだが……。
この記事に掲げた温泉マークは、この指摘を受けて描き直したものである。
ちなみに静岡県熱海市のマーク(市章)にもJISの向きで湯気の上がる温泉マークが用いられている。
さすが熱海だ。
また、公式の地形図記号もそれぞれの図式によって微妙に形状が変化している。
※本稿は、『地図記号のひみつ』(中央公論新社)の一部を再編集したものです。
『地図記号のひみつ』(著:今尾恵介/中央公論新社)
学校で習って、誰もが親しんでいる地図記号。地図記号からは、明治から令和に至る日本社会の変貌が読み取れるのだ。中学生の頃から地形図に親しんできた地図研究家が、地図記号の奥深い世界を紹介する。