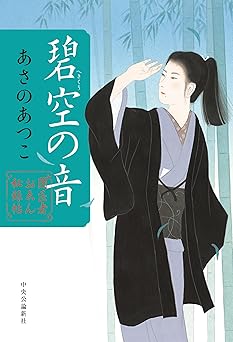「先生、駄目っ」
不意に腕を掴まれる。細い指が、食い込んできた。
「駄目よ、先生。一人で動いては駄目。何が起こるか、わからない。危ないことをしないで」
血の気のない顔の中で、黒い眸だけが熱を帯びてぎらつく。
「お小夜さん……」
「先生に何かあったら、あたし、どうすればいいの。お願いです。誰かを頼って。一人で動かないで。あたしは……あたしは、ここから出られないけれど……惣名主さまなら、何とかしてくれるかもしれない。先生、頼ってみて、お願い」
「御免だね」
お小夜の手をそっと外す。
「吉原惣名主を頼って、借りを作る。その方がよほど剣呑さ。喉元に刃を当てられているのと、変わりゃしないよ」
「……先生」
おゑんは片膝を立てると、お小夜の顎を軽く摘まんだ。
「お小夜さん、あんまり、あたしを舐めないがいいよ」
「え?」
「あたしはね、おまえさんが思っているほど弱くはないんだよ。他人(ひと)さまに頼らなくちゃ我が身を守れぬほど、弱くはないのさ」
「そんな、あたし……」
「頼りはしない。利用はさせてもらうかもしれないけどね」
指先ですっと、お小夜の頬を撫でる。滑らかで冷えた肌だった。
「あたしを信じな。一分でも疑うんじゃないよ」
お小夜が顎を引いた。口元に微かな笑みが浮かぶ。
「そうね、そうですね。あたしが惚れた相手だもの。そんなに柔ではありませんよね」
指をつき、優雅な仕草で頭(こうべ)を垂れる。
「大層な失礼をいたしました。お許しを」
おゑんも笑み、立ち上がる。
「それでは、また。近いうちに参りますよ、花魁」
「お待ちしておりんす」
座敷を出る。入れ替わりのように、髪結が入っていった。
吉原が動き出す。幻の花弁がゆっくりと開いていく。
段梯子を下りる。帳場に番頭の姿はなかった。そのまま草履を履き、総籬の前を行き過ぎる。女たちはまだ、座っていない。老女が一人、畳を拭いていた。
「先生、先生」
通りに出たところで、つるじが追いかけてきた。小さな身体が弾むような走り方だ。
「どうしたんだい。何か忘れ物でもしたかねえ」
つるじはおゑんの前に回り、見上げてくる。
「ねえ、先生。あたし、何か手伝える?」
「は? おまえ、あたしの助手(すけて)をするつもりなのかい」
「うん。そのつもり。あたし、先生が思っているより役に立つよ、きっと」
確かに、実の歳より大人びて、聡明で、気働きのできる禿は、何事においても人並み以上の仕事をするだろう。
「それ、お小夜さんに言われたのかい」
「ううん。あたしが自分で思ったの。先生の助手をやってみたいなって」
「そうかい、ありがとうよ。けどね、おまえは美濃屋の禿だ。あたしが勝手に使うわけにはいかないさ。おまえだって、ご主人にお叱りを受けるよ」
つるじの眉が下がった。かわいそうなほど気落ちした顔になる。
「そうか……やっぱり、そうだよねえ」
つるじがどういう経緯で吉原にいるのか。おゑんは知らない。知らなくていいことだ。ただ、この少女がいずれ、江戸随一の色里の花になることは定められている。そのいずれは、そう遠くない未来にやってくる。
だから、つるじは諦めることを知っている。望みを断つことを心得ている。諦めても、望みを断とうとも死にはしない。生き延びるコツをしっかりと掴んでいる。お小夜の許で、学んできた逞しさだ。
「ねえ、つるじ。それなら、おまえの耳を貸しておくれな」
「耳を?」
「そう。花魁の用で町に出るだろう。そのとき、誰がどんな話をしていたか、ちょいと耳をそばだてておくれ。でも、深追いはするんじゃないよ、聞き直したり、聞き出そうとしたり、それはご法度だからね。ただ、知らぬ振りをして、聞いているだけ。わかったね」
「うん、わかった。あたし、きっとそういうの得意だよ」
「そうかい。頼もしいじゃないか」
「ふふ、あのね、先生。先生だけに教えてあげる。花魁にも内緒のこと」
屈みこんだおゑんの耳元に、つるじは囁いた。
「あたしね、吉原のお話を書くの」
「は? どういう意味だい。草紙ってことかい」
「うん。あたし、ご本が大好きなの。読むのも好きだけど、書いてみたい。吉原のお話を書いてみたいんだ。花魁のこととか、他のお姐(ねえ)さんたちのこととか、番頭さんのこととか、お客さんのこととか……みんな、書いてみたいの。だから、いつか書くんだ」
それだけを告げると、つるじは踵(きびす)を返し美濃屋の中に消えていった。
おやまあ、何て子だろう。
つるじの息がかかった耳元にそっと手をやる。声の震えがまだ残っているようだ。
それじゃ、おまえの本を読める日をじっくり待つことにしようかねえ。また一つ、楽しみが増えたじゃないか。ありがとうよ。
もう一度、耳に手をやり、ついでにおくれ毛をかき上げる。
さて、あたしはあたしなりに、思案を巡らせなきゃならない。
風が吹いて、花の香りを運んでくる。この時季、仲の町の通りの真ん中に桜の樹と山吹が植えられるのだ。桜が満開になれば、雪洞(ぼんぼり)が幾つも点され、桜を下から照らしだす。日の光の中で見る光景とはまるで異質の吉原の夜桜が妖しく、美しく、闇に浮かび上がる。
人の力によって花の美を極めようとする試みだ。
それに感嘆するのか、気圧(けお)されるのか、愚かさを感じ取るのかは人それぞれだろう。吉原はどこまでも美しいものを極め、食い尽くそうとする。それだけだ。
「先生」
風に顔を向けたとき、呼ばれた。落ち着いた、低い声だ。
ちっ。舌打ちしそうになる。吉原で一番会いたくない者の声だったからだ。
寸の間で気息を整え、おゑんは急ぐでもなく焦(じ)らすでもなく、身を回した。
「おやまあ、これは惣名主じゃござんせんか」
「ええ。ご無沙汰しております」
吉原惣名主、川口屋平左衛門が頭を下げる。
白髪の小柄な老人だ。見ようによっては、好々爺(こうこうや)の隠居のようにも思える。とんでもない思い違いではあるが。おゑんはこの老人ほど、見場と正体が懸け離れている男を知らない。女は一人、二人、知っている。
「先生、お急ぎですかな。老人の相手をしていただく暇があれば嬉しいのですが」
「惣名主のお相手を? ごめんなさいよ。それは、あたしには些か荷が重うござんすね」
「何を仰います。先生ほど楽しいお相手はおりませんよ。あちらの茶屋で一服、お付き合いください。ぜひに、お願いいたしますよ」
「一服がお茶ならよござんすがねえ」
とんでもない毒を飲まされかねない。できるなら、誘いを断って立ち去りたいけれど、惣名主を振り切って大門を出ることは叶うまい。
「とびきり美味しいお茶を用意いたしますよ。さっ、先生、こちらへ」
平左衛門が歩き出す。
おゑんはため息を一つ吐き出し、空を見上げた。