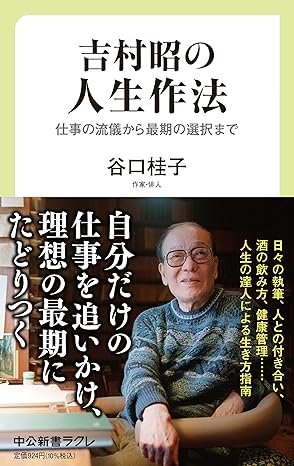吉村が外食したときには
編集者らと外で会食した吉村は、帰宅すると、「今夜の献立は何だった?」と必ずきいた。それが好物のものだと、一食損をしたような気分になったらしい。
〈亭主は丈夫で留守がよい、と言うが、わが夫は毎日家にいて、三度三度の食事と晩酌を楽しみにしているので、手のかかることこの上ない。〉(「別冊文藝春秋」昭和51年9月号)
なんのためにお手伝いがいるのだと言いながら、吉村が望んでいたのは愛妻の手料理だった。
「君は、小説さえ書いていればいいのだ」と言われて結婚した津村にとっては、これほどの誤算はなかったかもしれない。
※本稿は、『吉村昭と津村節子――波瀾万丈おしどり夫婦』(新潮社)の一部を再編集したものです
『吉村昭と津村節子――波瀾万丈おしどり夫婦』(著:谷口桂子/新潮社)
数々の名作を世に送り出した小説家夫婦――その人生は、愛とドラマに満ちていた。
「結婚したら小説が書けなくなる」。プロポーズをいなす津村を吉村は何度もかき口説いた。「書けなくなるかどうか、試しにしてみてはどうか」。そして始まった二人の人生は、予想外の行路を辿っていく。生活のための行商旅。茶碗が飛ぶ食卓。それでも妥協せず日々を積み重ねる二人に、やがて脚光が……。互いを信じ抜いた夫婦の物語。