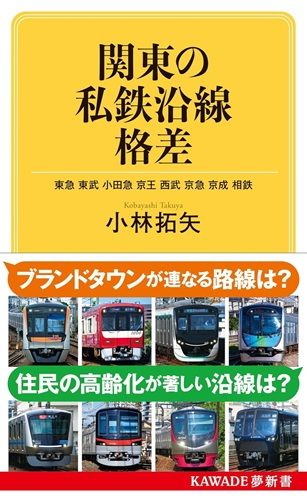新しい街が多い
小田急線沿線の基本的な特徴としては、沿線には高学歴・高所得層が多く、しかも近年完成した複々線化の影響もあって、鉄道の利便性まで向上するという、恵まれたポテンシャルを持っていることだ。
一方、もともとは農村部で、そこを開発して住宅地にしていったという経緯からか、比較的新しい街が多い。
開業は昭和に入ってからの鉄道であり、そこから沿線がつくられていった。
関東大震災後に多くの人が郊外に移り住むなかで、早く移り住んだ人は東急沿線に移住し、遅く移り住んだ人は小田急沿線にやってきたというところがある。
現在は、経済的にある程度裕福な人たち、社会的地位が高い人たちをターゲットにした沿線であり、その状況が現在も続いている。
また、教育面で学力競争よりも個性の尊重を大切にしているように感じられるのは、自由な校風で知られる玉川学園や和光学園が沿線にあるからだろう。
豊かな人たちがのびのびと暮らし、箱根観光などをときどき楽しむというのが、小田急沿線の特徴である。
※本稿は、『関東の私鉄沿線格差: 東急 東武 小田急 京王 西武 京急 京成 相鉄』(河出書房新社)の一部を再編集したものです。
『関東の私鉄沿線格差: 東急 東武 小田急 京王 西武 京急 京成 相鉄』(著:小林拓矢/河出書房新社)
関東8大私鉄の「沿線力」を徹底比較。住みやすさ、行政サービス、将来性、ブランド力、天災への強さなど、さまざまな視点から、知っているようで知らない「真の評価」を明らかにする!