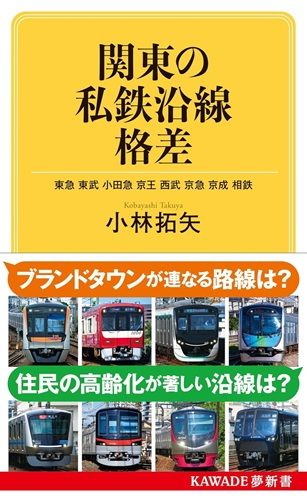沿線格差
東急沿線の豊かさを示すエピソードに、コロナ禍でテレワークが盛んになった時期の話がある。
東急沿線は、ほかの私鉄沿線に比べてテレワーク可能な企業や職種の人が多いため、利用者が大きく減ったということになった。これはいまでも完全には戻っていない。
しかし、テレワーク可能な企業や職種は、大企業のホワイトカラーであり、しかも経営判断が合理的なところである。
コロナ禍で確かに東急電鉄の鉄道事業収入は減ったが、このような現象が起こったこと自体、東急沿線でのライフスタイルの豊かさを示すものといえないだろうか。
創業当時から、「沿線格差」を意識して鉄道と関連事業を行ない、経済的にも文化的にも豊かな層が求めるものを提示し、多くの人を引き寄せてきたのが、東急グループである。
路線が長いわけでもなく、観光地などもないため、有料特急のような鉄道そのもので華がある事業はできないものの、鉄道事業、そして関連事業の発展が、地域社会の発展にも大きく貢献してきた。
東急電鉄は「沿線格差」の頂点に立ったといっても過言ではない。
※本稿は、『関東の私鉄沿線格差: 東急 東武 小田急 京王 西武 京急 京成 相鉄』(河出書房新社)の一部を再編集したものです。
『関東の私鉄沿線格差: 東急 東武 小田急 京王 西武 京急 京成 相鉄』(著:小林拓矢/河出書房新社)
関東8大私鉄の「沿線力」を徹底比較。住みやすさ、行政サービス、将来性、ブランド力、天災への強さなど、さまざまな視点から、知っているようで知らない「真の評価」を明らかにする!