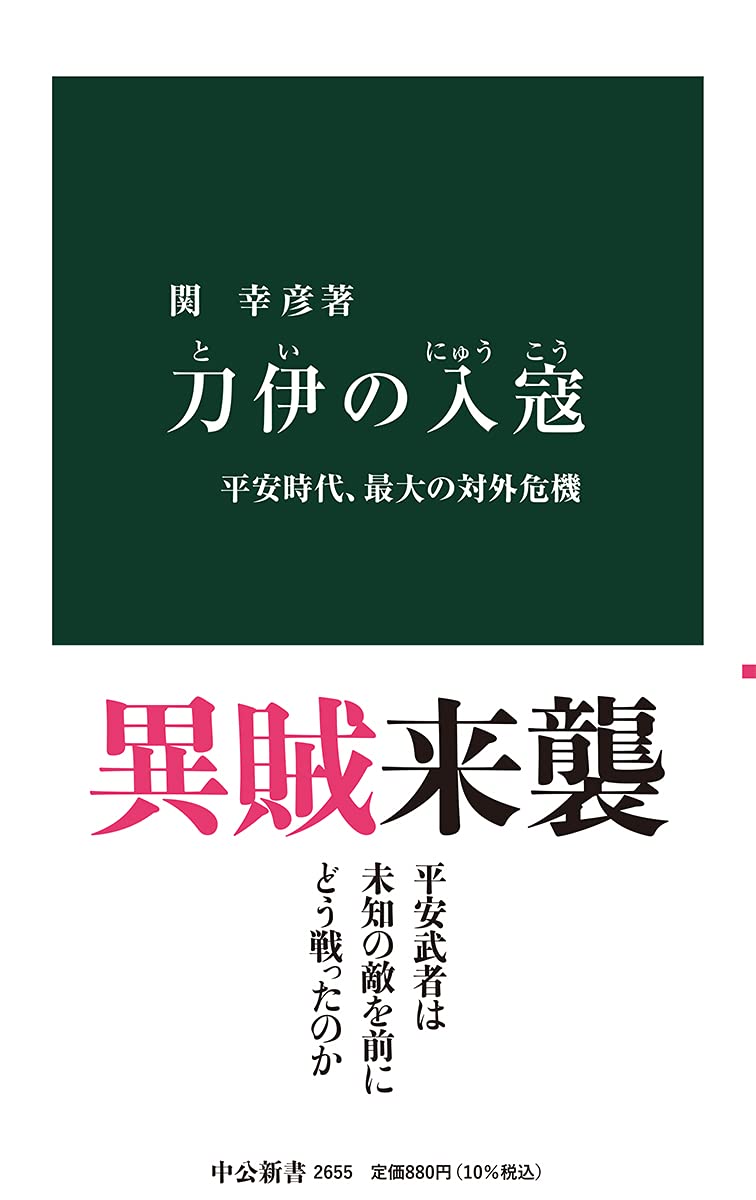盤石の体制にあったはずの道長時代だったが
こうした世情不安を重く受けとめた実資はすみやかな対策を主張、道長以下の公卿と協議し、検非違使(京の治安維持を担った役職)による夜間巡回の対策も講ぜられた。
刀伊来襲はそんな状況でのことである。4月25日「刀伊国ノモノ五十余艘、対馬島ニ来着、殺人・放火」との報が実資のもとに伝えられる。
刀伊襲来の時節、実資63歳、道長54歳、そして隆家41歳のそれぞれは、時を共有しつつも異なる環境に身を置いていた。実資そして道長は持病をかかえつつも、儀式・政務をこなし、放火・盗賊の治安の悪化への対応に迫られていた。
九州にあっては隆家が予期せぬ不測の事態への対応を迫られていた。11世紀前半の外交の危機は、盤石の体制にあったはずの道長時代に不安を招くことになる。
*本稿は、『刀伊の入寇-平安時代、最大の対外危機』の一部を再編集したものです。
『刀伊の入寇-平安時代、最大の対外危機』(著:関幸彦/中公新書)
藤原道長が栄華の絶頂にあった1019年、対馬・壱岐と北九州沿岸が突如、外敵に襲われた。東アジアの秩序が揺らぐ状況下、中国東北部の女真族(刀伊)が海賊化し、朝鮮半島を経て日本に侵攻したのだ。道長の甥で大宰府在任の藤原隆家は、有力武者を統率して奮闘。刀伊を撃退するも死傷者・拉致被害者は多数に上った。当時の軍制をふまえて、平安時代最大の対外危機を検証し、武士台頭以前の戦闘の実態を明らかにする。