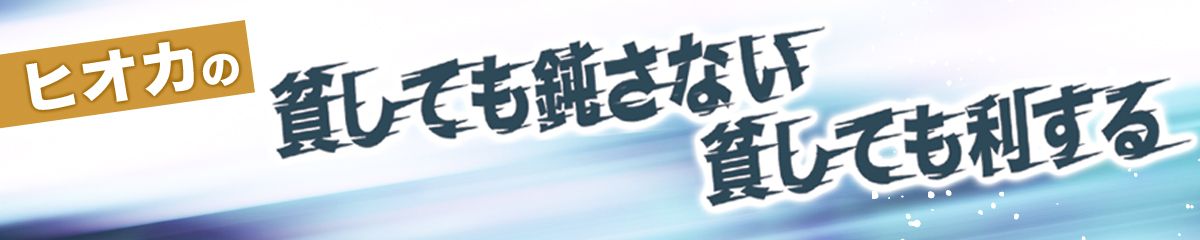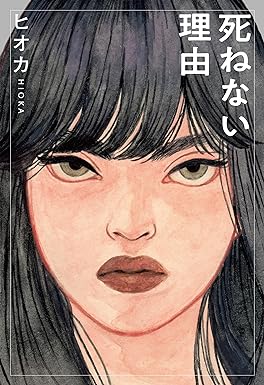私たちは影響し合って生きている
「弱者は優遇されている」「働かずに楽に暮らせてズルい」
そういう声は根強い。
しかし、本当に弱者になると全面的に優遇されて、人生イージーになるなら、望んで低所得者になる人がたくさん出るのではないか。実際その立場になりたいかと言えば、なりたくない人がほとんどだろう。
それは、心のどこかで、その立場になるとあらゆる不利益を被り、さまざまな制約をうけ、時に差別を受けて、圧倒的に不利な立場に置かれることを、心のどこかでわかっているからではないか。
前回の記事で、子持ちを「持つもの」、独身・子なしを「持たざる者」とする見方があるということを書いた。実際社会では、子育て世帯への支援が打ち出されると、「子持ちは優遇されている」という声があがる。しかし、子持ちは優遇されていると言う人たちが、夜中に夜泣きで何度も起こされてまとまった睡眠時間を取れず、しょっちゅう子どもが熱を出してそのたびに会社を休まざるをえず、同僚から迷惑そうな顔をされ、どこに行くにも何をするかわからない子どもと一緒で、気が休まらない立場になりたいか? と問われれば、多くの人は嫌だ、と思うのではないか。大きなマイナスを埋めるための「是正」を「優遇」と呼んでいる気がしてならない。
この社会では、生きやすさは奪い合い、トレードオフだと思われがちだ。年金制度をとっても、「若者vs高齢者」、会社では「独身vs子持ち」という対立構造になりやすい。
でも、私は生きやすさは奪い合いだとは思わない。低所得に陥っても、セーフティネットが用意されていて、障害を持っても、働き方が制限されない。そんな社会は、誰にとっても生きやすい社会だと思う。特定の属性が生きづらい社会は、他の人にとっても生きづらい。
すべての人が望めば質の高い教育を受けられる社会の方が優秀な人が育ちやすいし、医療へのアクセスが悪ければ、社会全体で負担する医療費が増大し結果みんなに影響が出る。
属性は時によって変化するものだし、同じ社会で生きている以上、私たちは見えないところで、関わり合い、影響し合って生きているのだ。