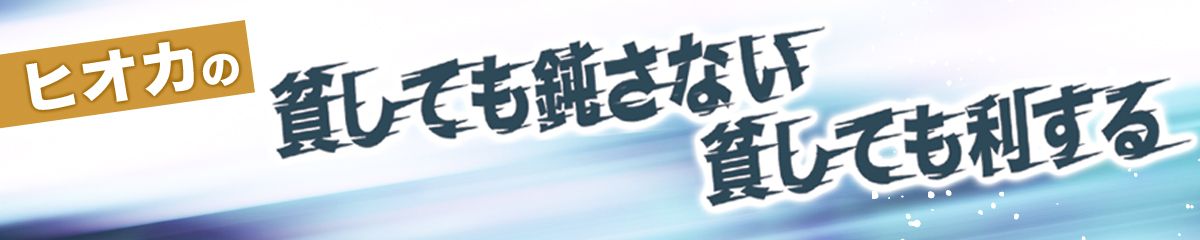「持つ者」「持たざる者」という視点
現在放送中のTBSの火曜ドラマ『対岸の家事〜これが、私の生きる道!〜』(原作、朱野帰子さん)が大きな話題を呼んでいる。父親の不在でワーキングマザーがワンオペになりがちで、保育園の呼び出しに母親がすべて対応した結果、抜けた分の仕事を補う部下からチクリと言われてしまう。同じ子育ての当事者なのに、どこか家事や育児に他人事で、仕事を抜けるなんて無理、と同じく働きながらも子どものために急な休みをとり早退もしている妻に言ってしまう夫。そんなリアルな描写がたくさんあり、見ながらとてもヒリヒリする。観る人を巻き込み、現代の問題を考えるきっかけを生む優れたドラマだと思う。
中でも印象的だったのが4話の「持つ者は持たざる者の気は知らず?」だった。タイトルに入っている「持つ者」「持たざる者」という視点で色んな問いかけがされていく。
「持つ者」「持たざる者」という視点の軸は主に二つ登場し、一つは「実家格差」の問題だ。対岸の家事では、様々な実家事情の登場人物が描かれる。主人公の村上詩穂(多部未華子)は、学生の時に、専業主婦の母親が亡くなってしまう。以後、仕事一筋の父親は家事を詩穂に押し付けるようになり、詩穂は高校卒業と共に実家を出た。以後、実家には一切帰っていない。詩穂のマンションのお隣さんである長野礼子(江口のりこ)は、夫が出張によく行っており、ワンオペ育児を強いられている。実家が遠くにあるため、両親を頼ることができない。詩穂の夫・虎朗(一ノ瀬ワタル)は、両親が早くに亡くなり、実家自体がない。詩穂のパパ友である中谷達也(ディーン・フジオカ)は、裕福で教育熱心な実家だが、母親から教育虐待を受けた過去があり、絶縁状態となっている。
頼れる実家があることは当たり前ではない。人それぞれに事情があり、実家の資本力や実家との関係性で、本人の生きる難易度は大きく変わる。長期休みには帰省し、子育てで両親や義実家を頼る。それが当たり前みたいな風潮がある中で、そんな当たり前がない人たちの存在が可視化されたことはとても意味があることだと思う。