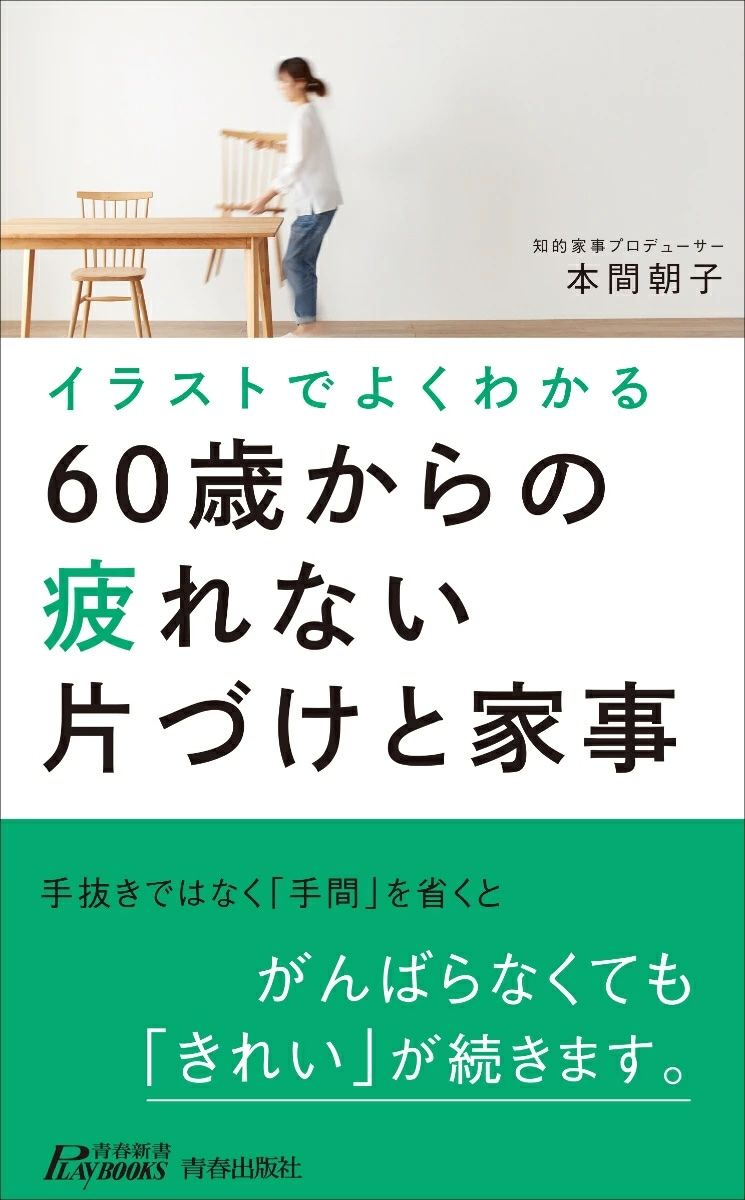「モノより自分を主役にする」が、疲れない家事のコツ
家事をしやすい環境を整える要素のひとつとして、モノの整理も含まれます。
モノは増えれば増えるほど、家事をめんどうくさく複雑にします。本当に必要なものだけを厳選し、あとは極力手放してしまったほうがラクになります。
モノを整理するときには、「まだ使えるかも」と捨てられない方、「もう使ってないから」と捨てられる方の2タイプいるようです。
「まだ使えるかも」と捨てられない方は、「そのモノがまだ使える」と、主語がモノになっています。
「もう使ってないから」と捨てられる方は「自分が使ってないから捨てられる」。主語は自分です。
なかなか捨てられない方は、人生の主役がモノになっていないか考えてみるといいでしょう。
どうしても捨てられないという場合は、寄付する方法もあります。
古着を送ると発展途上国のワクチンを寄付してくれる団体や、食料品であれば福祉施設、路上生活者などに寄付する団体もあります。
私は亡くなった祖母にもらったかいまきを長年手放せずいましたが、寄付することで収納スペースとともに気持ちの整理ができました。
それでも捨てられなければ、自分に何かあれば「捨てても構わないもの」「誰かに渡してほしいもの」といった分類だけでもしておくといいですね。
※本稿は『イラストでよくわかる60歳からの疲れない片づけと家事』(青春出版社)の一部を再編集したものです。
『イラストでよくわかる60歳からの疲れない片づけと家事』(著:本間朝子/青春出版社)
「きちんと暮らしたいけれど、体力的に日々の家事がつらくなってきた」「老後に向けて、いままで同様に家事ができるか不安」「夫婦2人になったので、もう少し手を抜いてもいいのではないか」
そんなシニアのために、知的家事プロデューサーである著者が「掃除」「洗濯」「料理」というカテゴリーで、家事の負担が減るアイデアやテクニックを教える、【疲れなくて、ちゃんと暮らせる家事】の提案。