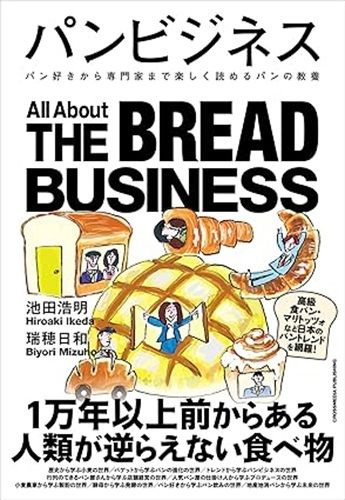パンがもつ“つなぐ力”
現代は食の価値観がより多様になり、シーンや嗜好によって選ばれる店も細分化されています。その中でベーカリーカフェは、「軽く食べたいけれど、しっかり満足したい」「一人でも立ち寄りやすい」「昼飲みをしたい」といった、多様で曖昧なニーズに応えることができる希少な存在です。またヴィーガンやグルテンフリーといった食の制限に対応したパンやメニューが増えていることも、支持を広げているポイントかもしれません。
さらに近年のコロナ禍で、人々の生活圏はコンパクトになり、地元でちょっと豊かな時間を過ごせる場所へのニーズが高まりました。そんな中で、地元で焼かれたパンや地域の野菜を使った料理、そこにワインやクラフトビールなどが加わることで、ベーカリーカフェは地産地消やスモールビジネスの魅力を象徴する場へと成長し始めています。人と人、人と食材、人と街をつなぐハブとしての役割もベーカリーカフェは担っているのです。
空間づくりも、こうした新しいパン屋さんの成功を語るうえで欠かせません。木の温もりを感じるインテリアや、自然光が差し込む大きな窓、さりげなく流れる音楽。居心地の良さはパンそのもののおいしさと同じくらい大切で、何気ない時間を「また来たい場所」に変える力を持っています。
このように、ベーカリーカフェが最注目の業態である理由は、決してパンが売れているからではありません。パンがもつ“つなぐ力”が、料理やお酒、そして人々の暮らしと交わることで、新たな食文化として根付き始めています。食べる楽しみを提案し、人とのつながりを生み出す――そうした意味でも、ベーカリーカフェは食のサードプレイスとして、今後さらに多くの人になくてはならない、憩いの場となっていくでしょう。
※本稿は、『パンビジネス』(クロスメディア・パブリッシング)の一部を再編集したものです。
『パンビジネス』(著:池田浩明、瑞穂日和/クロスメディア・パブリッシング)
なぜあのパン屋には行列ができるのか?
地方のパン屋が地域創生の核となれるのはなぜか?
パン飲みという新しい文化はどう生まれたのか?
単なる食べ物を超えた、パンの持つ力について考察を深めていきます。