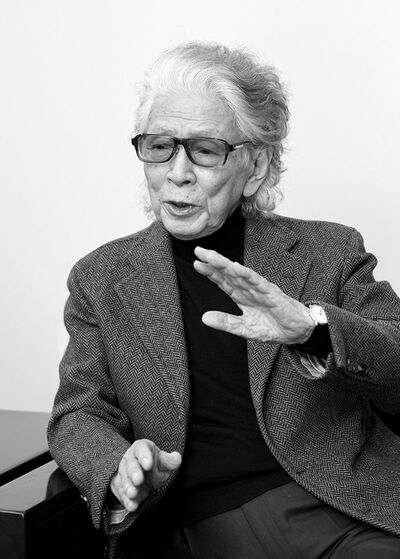封印されてきた負の記憶
冒頭で少しふれましたが、僕自身、かつて難民になった経験があります。いや、難民ではなく「棄民」と言うべきでしょうか。
父は敗戦前、朝鮮半島の平壌(ピョンヤン)で師範学校の教官を務めていました。当時12歳だった僕は、敗戦の詔勅がある数日前から、日本へ向かう飛行機がどんどん飛び立っているのに気づいていました。軍幹部、高級官僚、商社の幹部やその家族たちが、次々と内地へと帰っていたのです。
しかしラジオは、「市民は軽挙妄動するな。治安は維持されるので、そのまま現地にとどまるように」と繰り返し言っていました。その言葉を信じ、僕たち一家は8月15日以降もぼんやりと平壌にとどまっていたわけです。
後になって、「居留民に一斉に引き揚げられたら内地が混乱する」という理由で公式の引き揚げ作業が留め置かれた――つまり国から《棄てられた》のだと知った時は、激しい怒りを覚えました。
平壌にソ連軍が進駐してきて、日本軍を武装解除したのが9月中旬のこと。武器を捨てた日本の兵隊たちは、次々にシベリアへ送られていきました。それから正規軍が到着するまで、第一線のソ連兵は、乱暴狼藉の限りを尽くしたのです。その混乱のさなか、母を亡くしました。