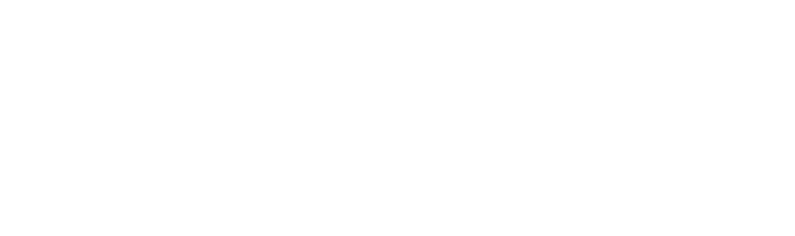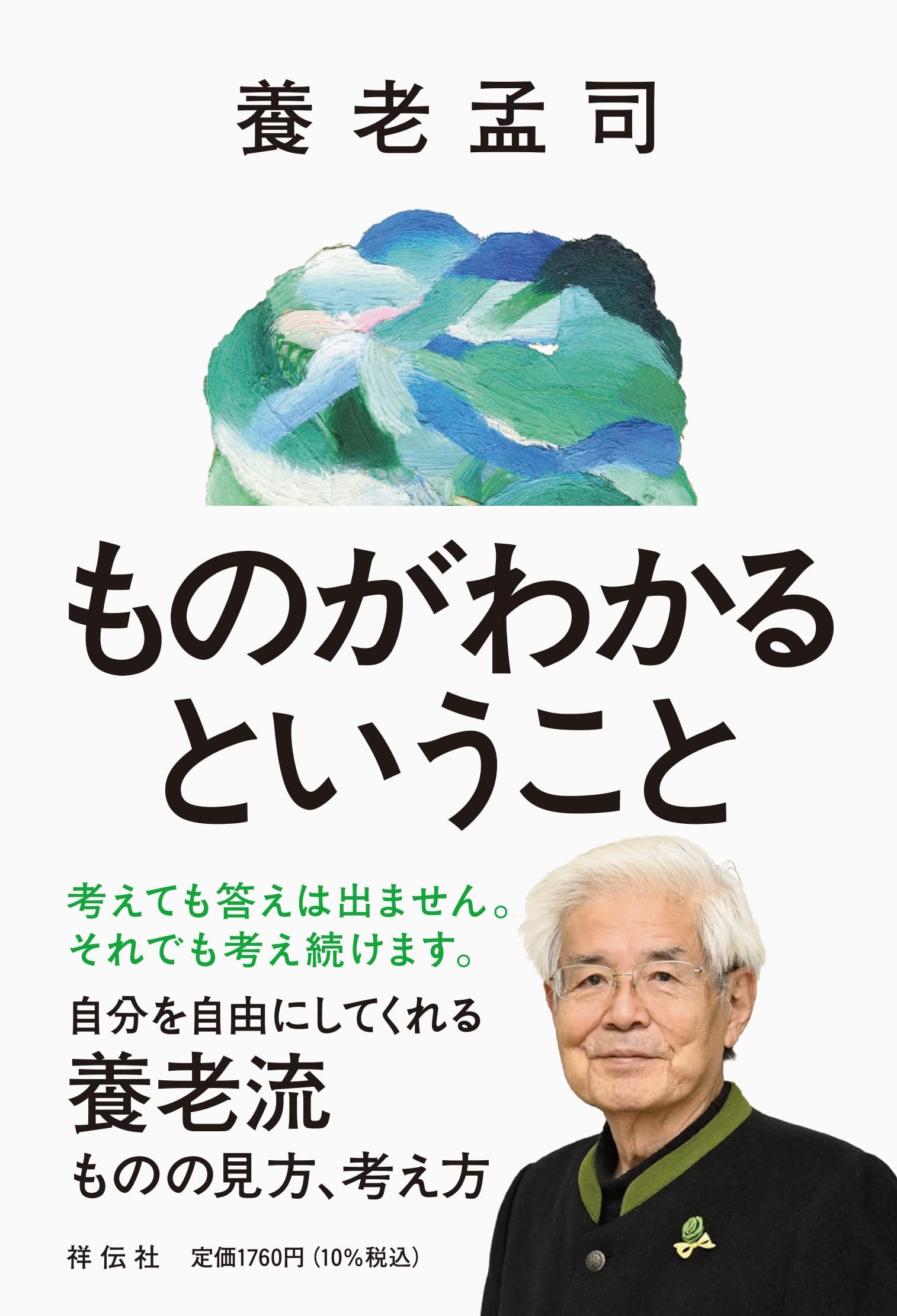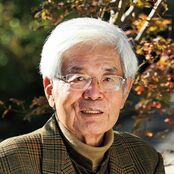「ああすれば、こうなる」を求めすぎている
また、本書では、「知っている」ことは「わかる」とは違うということも、さまざまな例を挙げて説明しています。
「知っている」は、他人同士が共通認識を持つための情報や記号を、知っているというだけ。「わかる」は、「腑に落ちる」という言葉があるように、身体的感覚を伴うもの。
そういった身体的感覚を、現代の私たちは忘れかけているような気がします。理由のひとつは、自然から遠ざかって生きているからでしょう。
自然は、「ああすれば、こうなる」というシミュレーション可能な原則に従って動いてはいません。人間の都合なんて知ったこっちゃないのです。ところがAI(人工知能)が進化し、人は何事にも「ああすれば、こうなる」を求めすぎるようになった。そこに大きな問題があります。
身体的感覚を取り戻すために、私は「現代の参勤交代」を提唱しています。都会を離れ、1年に1ヵ月でも田舎に身を置き、身体を使って働いたり、のんびり過ごしたりする。
猫を飼うのもいいかもしれません。猫が癒やしになるのは、「ああすれば、こうなる」が成立しないからです。
私は85歳になる今でも、海外にまで虫捕りに行きます。長時間飛行機に乗ることも苦になりません。無心になる時間を持つことで、心身のバランスがとれるんです。
女房の場合は、茶道でしょうね。茶道には、花や絵、書道の嗜みも必要。道具や器に触れることで触覚が刺激されますし、茶会では香も焚くので嗅覚も鍛えられている。五感をフルに働かせて、小さな茶室が森羅万象、つまり宇宙につながっていることを感じているわけです。日本の伝統文化は、本来そういった感覚を重視してきました。
自分の肌の内側だけを自分と思うのが現代人のありようです。でも、自分というのはもっと広いし、周囲の自然とつながっている。「わかる」をつきつめると、そんな考えに行きつく気がします。