好きなものができると、人生は豊かになる、幸福になると言われるとき、私は少しだけ苦しくなる。好きであればあるほど、私はたまにとても悲しくなり、つらくなり、そしてそのたびに私はその「好き」が、自分のためだけにある気がして、誰かのための気持ちとして完成していない気がして、いたたまれなくなる。好きな存在にとって少しでも、光としてある気持ちであってほしいのに、私は、どうして悲しくなるんだろう?
私は、宝塚が好きです。舞台に立つ人たちが好き。その好きという気持ちが、彼女たちにとって応援として届けばいいなと思っている。そして、同時に無数のスパンコールが見せてくれる夢の中にでも、悲しみもある、不安もある、そのことを最近はおかしいと思わなくなりました。未来に向かっていく人の、未来の不確かさをその人と共に見つめたいって思っている。だから、そこにある不安は、痛みは、未来を見ることだって今は思います。好きだからこそある痛みを、好きの未熟さじゃなくて鮮やかさとして書いてみたい。これはそんな連載です。
私は、宝塚が好きです。舞台に立つ人たちが好き。その好きという気持ちが、彼女たちにとって応援として届けばいいなと思っている。そして、同時に無数のスパンコールが見せてくれる夢の中にでも、悲しみもある、不安もある、そのことを最近はおかしいと思わなくなりました。未来に向かっていく人の、未来の不確かさをその人と共に見つめたいって思っている。だから、そこにある不安は、痛みは、未来を見ることだって今は思います。好きだからこそある痛みを、好きの未熟さじゃなくて鮮やかさとして書いてみたい。これはそんな連載です。
舞台のあの人と目が合った!とか、そういうの、「錯覚かもしれないのですが……」と付け加えたくなる私と、いやあれは目が合いましたよ!と自分の躊躇を後ろから羽交い締めにして叫びたくなる私もいて、もうこれは私の心と気合の勝負ではないかとたまに考える。
目線のこと。私は舞台を見に来ているのだし目が合うとかそういうことが観劇の全てではない……という気持ちもたしかにあるはずなのに、目が合ってるときのその役が急激に特別なリアリティを持つあの威力はとてつもなくて、特にその物語や役やそして演じている人に思い入れがあると、目から入ってきた情報でそのまま脳が焼き切れてしまいそうな感覚になるんです。おかげで、目が合った日には観劇後本当にその話しかできなくなる感じがして、「目線が!全てだと!思ってるみたいになってる……!」と自分でもいやになってくるし、そもそも人にこのことを話そうとしようものなら「目が合った……気がしたんですけど」とか「錯覚、なんですけどね」を付け足してしまい、私は脳が焼き切れておいて何を今更濁しているんだろう……と自分にうんざりもするのです。目が合ったんなら合ったんだよ、焼け切れた脳が証拠!と思いながら、そう言い切れないのは、自分が舞台という場に期待していた以上のものを受け取ってしまったことへの動揺ゆえなのかなぁ。この原稿はなぜ、私は、目が合った時にそう断言できないのか、ということを考える原稿です。考えなくてもいいことを考えてる気がする。
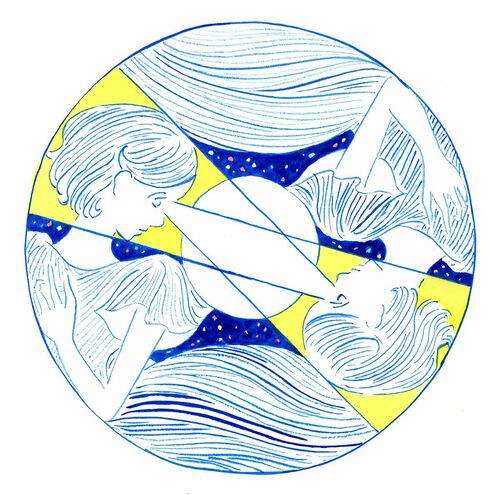
(イラスト◎北澤平祐)

