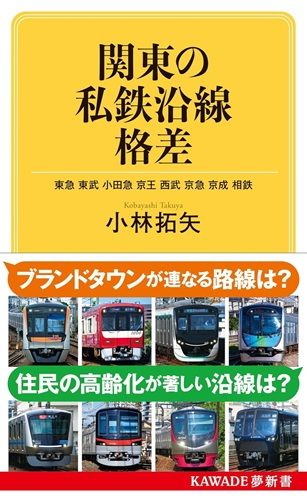成田スカイアクセス線
開業以来長く、通勤輸送と成田山への参拝者輸送を中心とした庶民的な路線として運行してきた京成電鉄は、1978(昭和53)年5月に成田空港に乗り入れ、「スカイライナー」の運行を開始した。
成田空港への輸送は、京成グループの鉄道部門において、それまで手がけてきたものと並ぶ大きな柱として育っていく。成田空港への乗り入れにより、京成電鉄の存在感は一気に高まった。
この間、大きな投資への失敗による経営難があったものの、1991(平成3)年3月には成田空港のターミナルビルに乗り入れ、空港と直結(それまでは駅から連絡バスを乗り継いでいた)する。
2010(平成22)年7月には成田スカイアクセス線が開業し、日暮里乗り換えというハンデをくつがえす最高時速160キロの速達性で、支持を集めるようになった。
成田山新勝寺参詣を目的としてつくられた京成電鉄は、通勤輸送を手がけつつ、成田空港アクセス鉄道にも力を入れている。
都心から離れたところでの利用が多いという特徴を持つために、都市社会の構造を示す沿線となっているのが、京成電鉄沿線である。
※本稿は、『関東の私鉄沿線格差: 東急 東武 小田急 京王 西武 京急 京成 相鉄』(河出書房新社)の一部を再編集したものです。
『関東の私鉄沿線格差: 東急 東武 小田急 京王 西武 京急 京成 相鉄』(著:小林拓矢/河出書房新社)
関東8大私鉄の「沿線力」を徹底比較。住みやすさ、行政サービス、将来性、ブランド力、天災への強さなど、さまざまな視点から、知っているようで知らない「真の評価」を明らかにする!