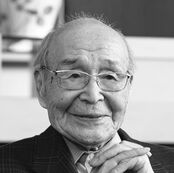連歌のやりとりは粋なコミュニケーション
楽しみといえば、数人が集まって「発句」から始まり、次々と下の句、上の句をつなげていく「連歌」も、とても楽しいものです。以前は、大岡信さん、丸谷才一さんと、神田の蕎麦屋の2階でよく歌仙の会をやりました。
丸谷さん、大岡さんは亡くなりましたが、今は長谷川櫂さん、三浦雅士さんと歌仙の会を続けています。コロナ前までは銀座のバーに集まってやっていたのですが、コロナで会えなくなってからはメールを使っています。
今日も、息子がプリントしてくれたものが目の前にありまして。2、3日うちには書いて、次の人に送る予定です。たとえ直接会えなくても、つながっていられますから、孤独が癒やされる。連歌は、男女性別が違っていても、年齢が離れていても、共同制作を楽しめる素敵な遊びだと思いますよ。
それにしても、まぁ、長い人生でしたし、思い起こせばいろいろなことがありました。もちろん年齢とともに詠む歌も変わってきました。青年期には、やはり異性を意識するというか、恋愛感情のなかでどう生きていくかということが人生の大事な意味になるわけですから。自然と色っぽい歌が生まれます。
軍隊での厳しい生活、鉄拳制裁も経験したし、結婚をし、子どもや孫、そしてひ孫にも恵まれた。それらもすべて、歌として残っています。
とにかく、一生作り続けてきましたからね。散文を書く前に、まず歌の形で自分を表現したい。思いが自然と三十一文字になって流れ出てくるのです。本当にありがたいことだし、幸福な運命を生かされてきたと思います。