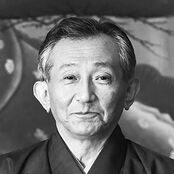第2の転機となるのは、シテ方能楽師に共通して言える大曲『道成寺』の初演、ではないだろうか。
――はい。23歳の時でした。これで大人の能役者の仲間入り、とも言える曲でもあるのです。これを演らせていただけることはものすごく嬉しい。舞い終えたあと、他の曲にない充実感があるのです。
あの時、簡単な打ち上げで飲んだビールの最初のひと口目。美酒に酔うとはこのことかと思いましたね、偉そうに。(笑)
まぁ、この曲の初演までは山あり谷ありの道のりでしたから。たとえば「乱拍子」は、白拍子が鐘を目指して寺の石段を一段一段登る様子を特殊な足遣いで舞いますが、これは小鼓方と一対一で、真剣勝負のような稽古を重ねるのです。
その時は小鼓の先生の《息を盗む》わけですよ。父はやはり心配だったんでしょう。「息は盗んでも罪にはならないのだから、しっかり盗めよ」とね。
先日、息子の三郎太が『道成寺』を初演しましたが、その稽古の時、いつの間にか自分が父と同じ言葉を息子に掛けていて、何か胸に迫るものがありました。