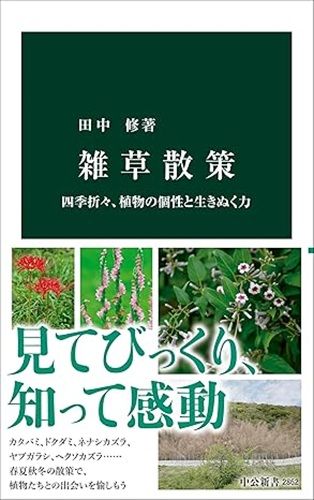変わった名前の草
雑草にも、いろいろ気になる名前の植物がありますが、ここでは、ハキダメギク、ワルナスビ、ウマノアシガタを紹介します。
ハキダメギクは、この名前から、「どんな汚いキクなのか」と思われるでしょう。あるいは、「掃き溜めにツル」にならって、「掃き溜めにキク」なら、どんなにきれいなキクかと思われるかもしれません。
花はキクに似てきれいでかわいいです。食べ物の残りや生ゴミが捨てられるゴミ溜め場や堆肥の置かれるような道端に生えるキク科の植物です。掃き溜めのような場所に生えるからハキダメギクといわれるのですが、汚い場所を好むのではなく、栄養の豊富な土地の肥えた場所を好むのです。これは熱帯アメリカが原産地で、漢字名は「掃溜菊」です。
ワルナスビは、「いったい、何が悪いのか」と思われるような名前です。花や葉っぱの形はナスに似ていますが、鋭いトゲがあります。だから、この雑草を刈ったり抜き取ったりしようとすると、手ごわい植物です。そのため、やっかいな草と思われ、こんな名前がつけられたのです。これはナス科で、北アメリカ原産で、漢字名は「悪茄子」です。

ウマノアシガタ(馬足形)は、身近な野や道端、土手や水田の畦に生え、草丈が30〜60センチメートルになると、晩春から初夏に花が咲きます。直径1〜2センチメートルの光沢のあるあざやかな黄金色に輝く5弁の花です。この花の様子から、「なぜ、ウマノアシガタなのか」との疑問が浮かびます。
「冬を越す葉っぱの形がウマの足形のようなので、この名がついた」といわれますが、実際には、その葉っぱはウマの足形には似ていません。むしろ、トリの足跡に似ているので、ウマとトリをどこかで間違ったのではないかといわれます。
正式な和名は「キンポウゲ(金鳳花)」です。英語名の「バターカップ(buttercup)」は、光沢のある花の形にちなみます。この植物には、「プロトアネモニン」という有毒物質が含まれています。キンポウゲ科の植物で、原産地は、日本や中国、朝鮮半島です。

※本稿は、『雑草散策-四季折々、植物の個性と生きぬく力』(中央公論新社)の一部を再編集したものです。
『雑草散策-四季折々、植物の個性と生きぬく力』(著:田中修/中央公論新社)
歩道の片隅、建物の陰、池の水面……街を歩くとあちこちで雑草に出会う。
ひっそりと、時には堂々と生えている雑草には、どんな生きぬく力があるのだろう?
四季折々の身近な雑草を案内役に個性豊かな植物の生きぬく力を紹介。