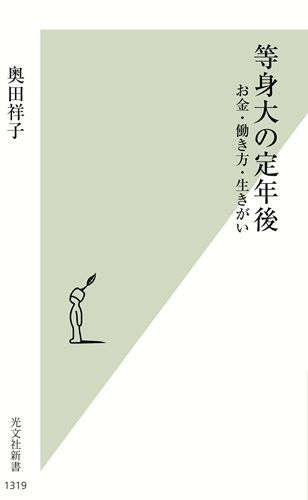私生活の充実と「先は気楽に」
そうして、私生活の充実も、田川さんにとって定年後を心地よく過ごすにあたって欠かせない重要なことだった。2つ目と3つ目の変化は、趣味の充実と、夫婦関係の改善である。
仕事の忙しさから30年以上も途絶えていた趣味の登山を50歳で再開し、妻とともに月に1度は山に登るようになったことで、ストレスの多かった状態から、健全な心身を取り戻していったという。
「自然を五感で楽しむことで、40代で悩んでいた、出世できなかったことや年下上司とのギクシャクした人間関係がなんてちっぽけなことだったのか、と思えた。大袈裟かもしれませんが、いろいろと経験を積んだ末の登山で、世界は広いんだということを、若い時とはまた違って感じることができたんです。本当にうれしかった。大学の登山部の後輩で専業主婦の妻とは年を重ねるにつれて会話が少なくなっていましたが、一緒に山に登ることで共通の話題も増え、良好な夫婦関係を築けるようになりました。定年後の仕事は、やっぱり私生活の充実とセットでこそ、うまくいくと思いますね」
24年春、田川さんは1年ごとの再雇用の契約を更新した。65歳までは働き続けたいと考えている。ただ、現時点では今の会社には、66歳以降の継続雇用制度はない。どう考えているのだろうか。
「何も考えていません。あっ、ははは……。この春に61歳になったばかりで、まだ4年先のことですから……。まあ、そう気楽に考えることができているから、今も仕事を続けられているのかもしれませんね。少しでも必要としてくれる会社、職場があれば、働きたいとは思っていますが……」
どこかで見た表情、だと思った。顔にシワが増え、頭髪が黒から白髪交じりのグレーに変わりはしたものの、18年前、初めて取材した時、メンタルヘルス対策の重要性について熱く語った顔つきに似ていた。
※本稿は、『等身大の定年後 お金・働き方・生きがい』(光文社)の一部を再編集したものです。
『等身大の定年後 お金・働き方・生きがい』(著:奥田祥子/光文社)
日本では急速な少子高齢化の進行を背景に60歳を過ぎても働き続けることが可能な環境整備が進んでいる。
働く側も経済的理由だけでなく生きがいや健康維持などさまざまな理由で定年後の就業継続を望むケースが増えている。
本書では、再雇用、転職、フリーランス(個人事業主)、NPO法人などでの社会貢献活動、そして管理職経験者のロールモデルに乏しい女性の定年後に焦点をあて、あるがままの〈等身大〉の定年後を浮き彫りにする。