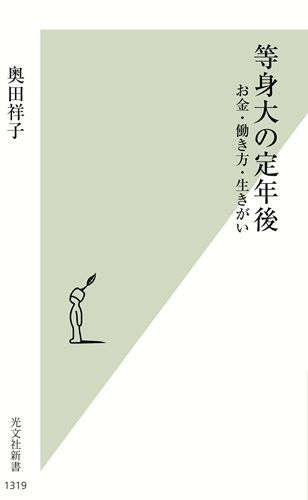改めて思いを尋ねると……
24年春、改めて思いを尋ねた。
「過去の肩書など通用しないし、長年地域に関わってこなかったハンデは百も承知していたつもりでしたが……ご近所さんであるボランティア同士の人間関係が煩わしかったのと、たまたま、登下校を見守る小学生の中に広報部時代に面識のあったマスコミ関係の人のお子さんがいて……家族の食卓で『部長から、見守りおじさんに転身』などと揶揄されているのではないかと想像して後ろめたい気持ちにもなって……。活動の対価が支払われない無償労働にやるせなさを感じたのも、そもそもボランティア活動への敬意と理解が足りなかったのだと思います。地域で人の役に立つ活動を安易に考え、動機も不純だったんでしょうね。会社で自分の手でCSR活動を軌道に乗せられなかった無念を晴らす面もありましたからね……」
ボランティア活動も仕事もしていない。これからどう過ごしていくつもりなのか。
「今年58歳の誕生日を迎えますが、会社の同期や大学の同級生たちはみんな管理職を退いても平社員として働いていますし、今は定年を過ぎても働き続ける時代ですからね……。しばらく休んで考えてから、有償労働に就くのか、ボランティアを再開するのか、何らかのかたちで、社会貢献につながる活動に関わりたいとは思っています」
前向きな時もつらい時も、ピンと張り詰めた空気が漂うことが多かったが、この時は肩の力が抜けたように、終始和やかな雰囲気だった。
※本稿は、『等身大の定年後 お金・働き方・生きがい』(光文社)の一部を再編集したものです。
『等身大の定年後 お金・働き方・生きがい』(著:奥田祥子/光文社)
日本では急速な少子高齢化の進行を背景に60歳を過ぎても働き続けることが可能な環境整備が進んでいる。
働く側も経済的理由だけでなく生きがいや健康維持などさまざまな理由で定年後の就業継続を望むケースが増えている。
本書では、再雇用、転職、フリーランス(個人事業主)、NPO法人などでの社会貢献活動、そして管理職経験者のロールモデルに乏しい女性の定年後に焦点をあて、あるがままの〈等身大〉の定年後を浮き彫りにする。