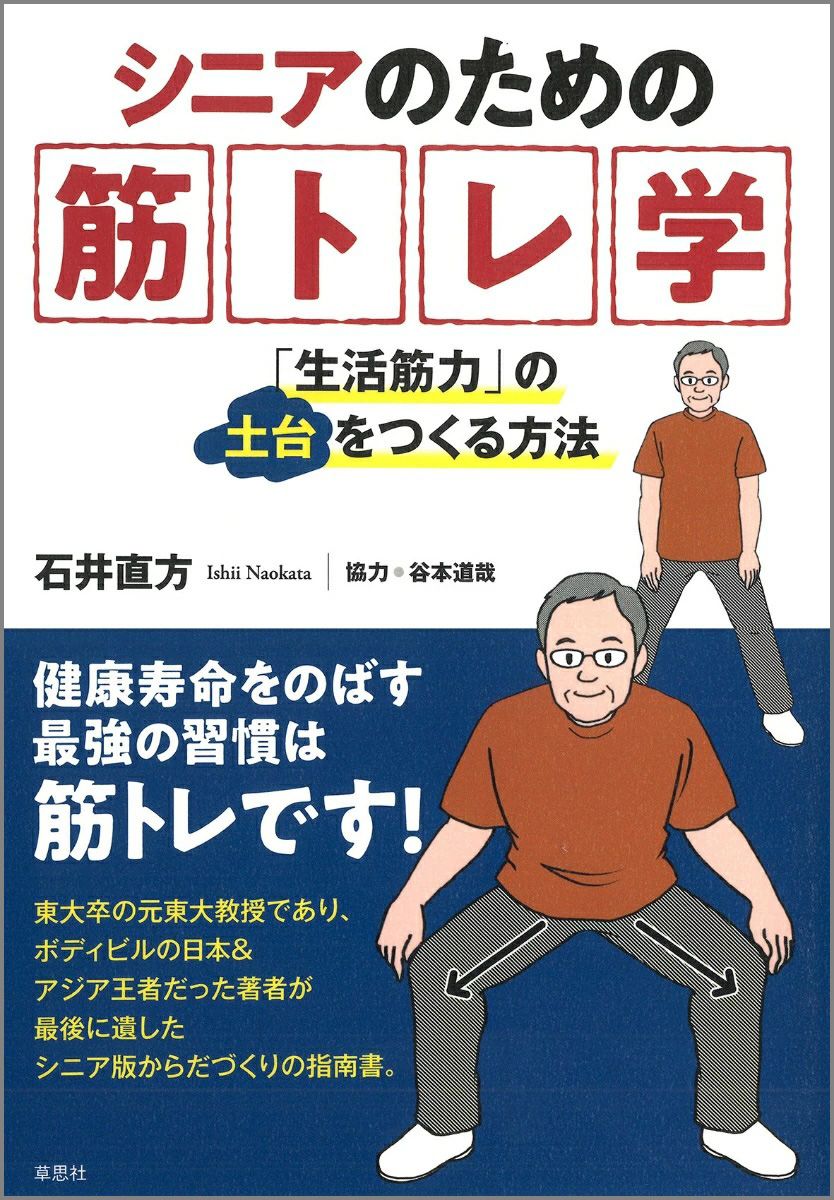転倒が原因で寝たきりになってしまう高齢者
実際、高齢者には、転倒が原因(例えば、大腿骨の骨折など重篤なケガによって)で寝たきりになってしまうというケースが少なくありません。
あるいはそれが原因で生じたケガから死に至ることさえあるのです。転倒を侮ってはいけません。
転倒は、筋力のある若い人でも不注意で転ぶことがありますが、筋力が低ければ、ちょっとした段差であっても、そのリスクはより高まってきます。
例えば、中高年になるといつも利用する階段であっても、つまずいてしまうことがあります。なぜか。
それは脚筋力の低下によって、段差をクリアできるところまで足を持ち上げているつもりであっても、実際には持ち上がっていないということが起こり得るからです。
ほんの数ミリ程度だと思いますが、実際の筋力と自身のいつもの感覚に誤差が生じてしまっているのです。
すなわち、それは備蓄していた余力がそろそろ尽き始めてきているという証しでもあるのかもしれません。
知らず知らずのうちに筋力が低下しているというのは、そうした日常のふとした場面においてもたびたび垣間見られます。
これは決して偶発的ではなく、筋力の低下による必然ということを理解しておくことが大切です。なにしろ、日常にはこうした危険がたくさん潜んでいるのですから。
※本稿は『シニアのための筋トレ学 「生活筋力」の土台をつくる方法』(草思社)の一部を再編集したものです。
『シニアのための筋トレ学 「生活筋力」の土台をつくる方法』(著:石井直方・協力:谷本道哉/草思社)
健康寿命をのばす最強の習慣は筋トレです!
平均寿命と健康寿命の差を縮めて、いかに長く自立した生活を続けるか――。
本書は、その鍵を「筋肉=生活筋力」に見出した実践的な指南書です。
加齢にともなう筋力低下やフレイル(虚弱)、ロコモ(運動器症候群)、サルコペニア(筋肉減少症)などが健康寿命を縮めることをわかりやすく説明しつつ、筋力維持の重要性を豊富なエビデンスと実体験を交えて解説しています。筋トレをはじめるのは、「何歳からでも遅くない」と励まされる内容です。