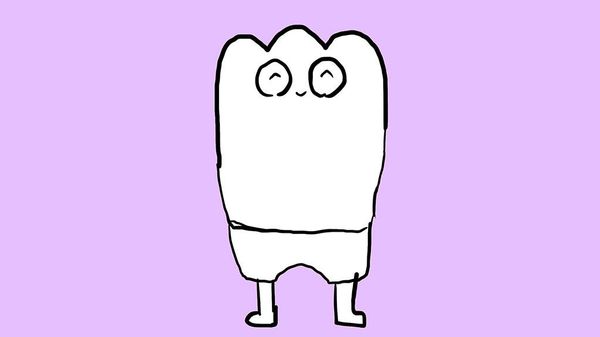当時は母に虐待されている感覚はなかった
母とふたりで暮らしていた田舎の小さな団地を飛び出してから、10年以上が経ちます。家を出たきっかけは、高校3年生のときに、僕がゲイであること、そして売春をしているのが母にバレたこと。
「あんた、男に体売ってるやろ……。くそホモ! 恥さらし! 出て行け!」と罵詈雑言の限りを尽くされましたが、「なぜそんなことをしたのか」と聞かれることは一度もなかった。子どもの過ちを叱る“親”ではなく、徹底的に“自分”であり続け、感情をぶつけるだけなのだな、と冷静な気持ちになったことを覚えています。
話しても理解してもらえることはないだろうと思い、バイトや売春で貯めたお金、通帳と印鑑、携帯電話だけを持って、高校の卒業式を目前にゲイタウンがある東京へ原付バイクを走らせたのでした。
母は、僕が物心ついたころには、たまにパートに出るだけの、ご飯もろくに作ってくれない、ゲームセンターに通ってばかりいる人でした。11歳年の離れた姉から聞いた話では、僕が6歳のときに父が自殺してから経済的な不安を抱えるようになり、人が変わってしまったそうです。家計は生活保護に加え、姉が高校に通いながら週6のバイトをして支えてくれていました。
暴力こそなかったものの、僕はいつも母から怒られていました。今振り返ると、ずいぶん理不尽な怒られ方をされていたと思います。母のジュースを飲んだからとゴミ袋に入れられたり、化粧をする場所だからダイニングテーブルで食事をするなと言われたり、「タッキー(滝沢秀明さん)みたいな息子がよかったのに、あんたなんて産みたくなかった」と言われたり──。また、僕の些細な一言で怒り出し、突然包丁を突きつけられたこともあります。あのときはさすがに血の気が引きました。
不思議に思うかもしれませんが、当時は虐待されているという感覚はなく、親子喧嘩の延長のように思っていたのです。経済的なことや母との不和を除けば、姉は優しかったし、友達や学校の先生にも恵まれたことが心の支えになっていたから。特に中学時代の恩師は僕にきちんと向きあってくれて、この先生に出会っていなければ今の僕はなかったと思うほどです。
あとは、単純に親から逃げる方法がわからなかった。今みたいにインターネットが盛んではなかったから、情報もなかったですしね。それに母から、「不細工」だのなんだのとけなされてばかりいて自己肯定感が低かったこともあり、大人である母の言うことのほうが正しいと信じてしまっていたのだと思います。